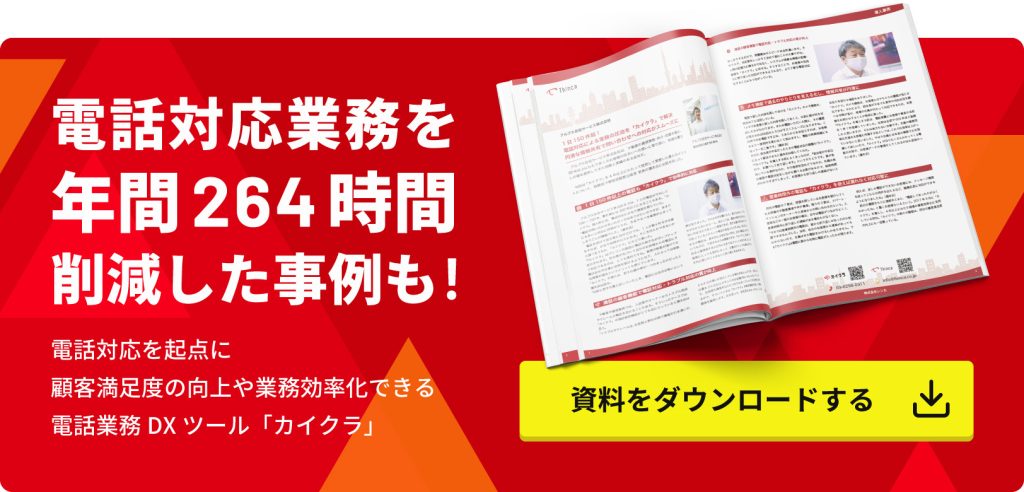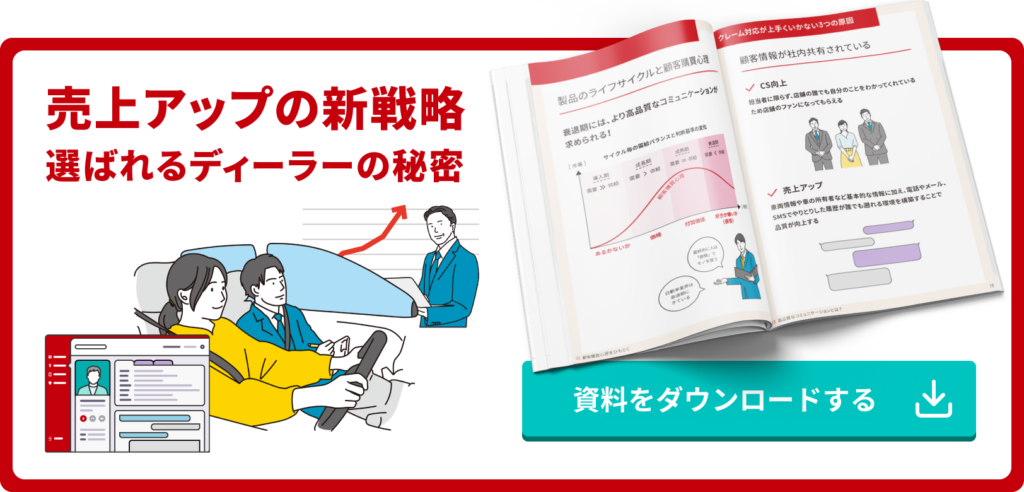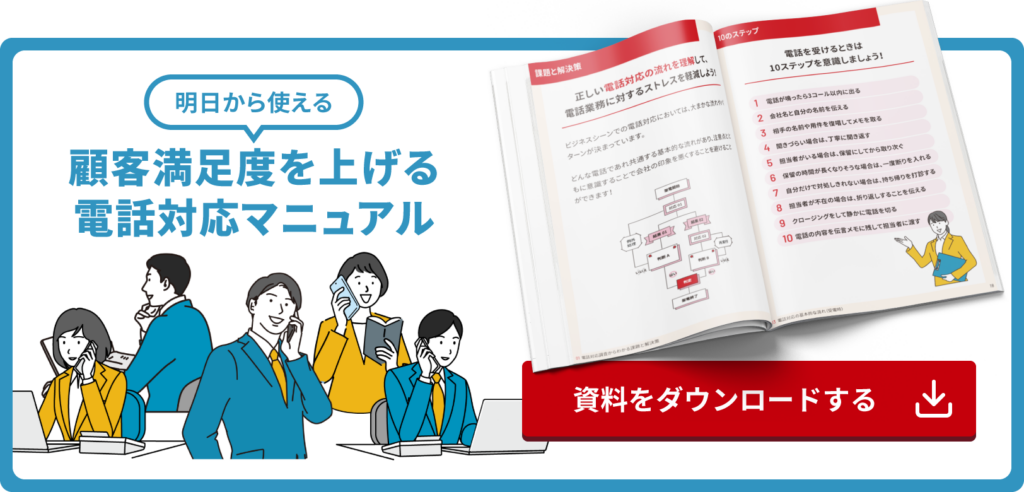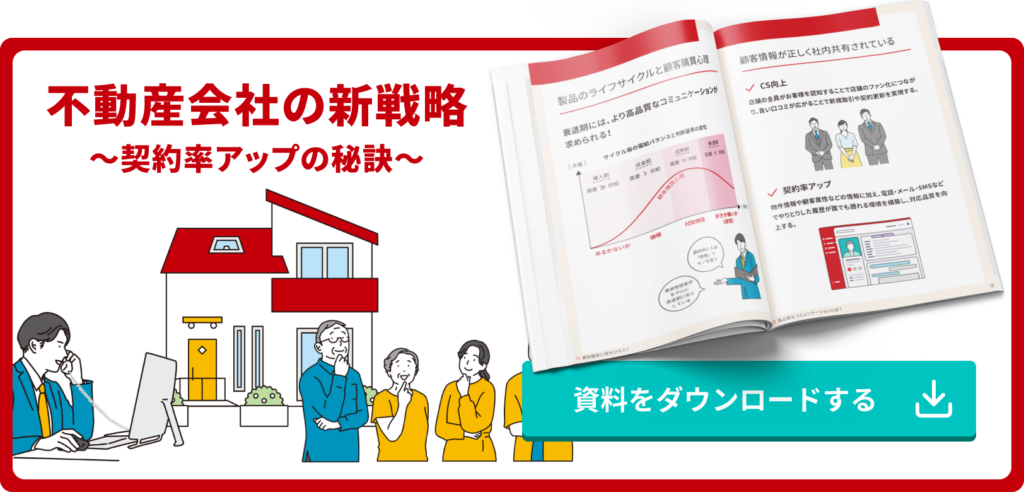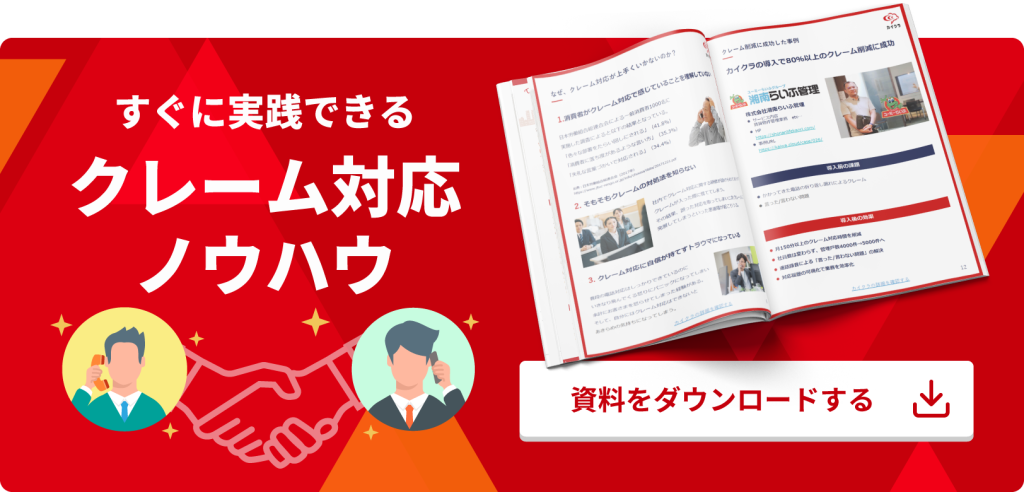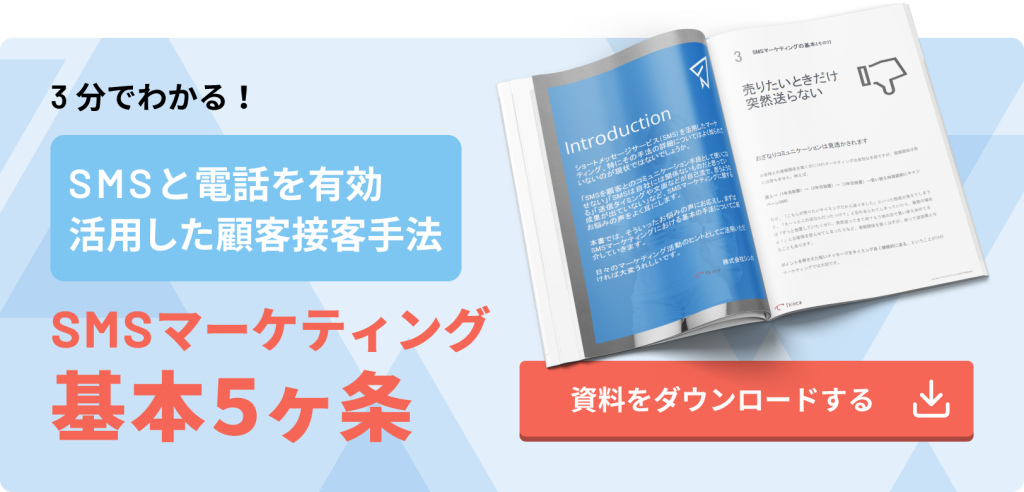電話恐怖症とは、電話に出るまたは出ようとすると心身症状をともなう苦痛を感じる状態で、電話をする機会が少ない方に多くみられる症状です。
電話恐怖症の社員が電話対応を続けていると、体調を壊し離職につながる恐れがあるため、部署移動が難しい場合は、電話恐怖症を克服するためのサポートが必要です。
「とはいえ、何から始めたらいいのかわからない」という方に向けて、この記事では電話恐怖症の克服に効果的な方法を紹介します。記事後半では電話恐怖症対策におすすめのシステムも紹介しますので「電話恐怖症の社員をサポートしたい」という方はぜひご覧ください。
なお、電話恐怖症対策のひとつとして、マニュアルの用意があります。
多用するフレーズを記載したマニュアルが手元にあれば、マニュアル通りに伝えるだけで電話対応ができるので、電話に恐怖心がある社員の心理的な負担を減らすことができます。
シンカでは、今すぐ使える電話対応マニュアルを無料で配布していますので、以下からダウンロードの上ご活用ください。
\明日から使えて電話対応時間を削減!/
カイクラの電話対応マニュアルをチェック
▲無料ダウンロードはこちらから
電話恐怖症とは?概要や症状を解説

電話恐怖症とは、電話に出ようとすると恐怖を感じ、心身に悪影響がでる症状です。
正式に病気として認定されているわけではありませんが、社交不安障害と近い症状が発生します。具体的な固定電話恐怖症の症状は下記の通りです。
▼電話恐怖症の症状
精神的な症状:不安、イライラ、動悸など
身体的な症状:過呼吸、身体の震え、頭痛、動悸、腹痛など
電話対応は、企業の印象を左右するため、売上アップにもつながる重要な業務のひとつです。電話に対して不安や恐怖を感じる社員がいる場合は、顧客に対して気持ちの良い電話対応ができるようにサポートしましょう。
ここからは、電話恐怖症の具体的な対策法を紹介します。
これで解決!電話恐怖症の対策法5つ

電話恐怖症の対策方法は以下の5つです。
- マニュアルの作成
- 電話対応時に使えるフレーズの用意
- メモテンプレートの活用
- 電話対応の研修
- 電話対応しやすい環境の整備
どれも大切ですが、とくに環境の整備は効果的です。それでは、ひとつずつ紹介します。
【対策1】マニュアルの作成
まず最初に取りかかりたいのはマニュアルの作成です。
マニュアルに対応の流れやフレーズを具体的に記載することで、全体の流れが明確になり自信を持って対応できる助けとなります。
また、マニュアルを頼りに電話対応を経験していくうちに「多くの顧客に対応した」という自信にもつながるので、恐怖心の軽減も期待できます。
「マニュアルは会社が用意するもの」と思うかもしれませんが、社員個人が作成するのもおすすめです。
マニュアルを作るために自分の知識や理解度を整理することで、現状の苦手が見えてくるという利点があるからです。苦手な部分を同僚や先輩に相談すれば、電話上達のコツを教えてもらえるかもしれません。
とはいえ、マニュアルを何もないところから作るのは時間がかかる場合もあります。もしベースとなるマニュアルが欲しい方は、以下から無料でダウンロードしていただけますのでぜひご活用ください。
\明日から使えて電話対応時間を削減!/
カイクラの電話対応マニュアルをチェック
▲無料ダウンロードはこちらから
【対策2】電話対応時に使えるフレーズの用意
電話対応時に使えるフレーズを用意することも、電話恐怖症の方に効果的です。
事前に用意されたフレーズを使うことで「電話対応特有の言葉遣いがわからない」という不安を軽減できます。
また使えるフレーズがあることで、状況に応じた対応が容易になり、スムーズなコミュニケーションの助けとなるでしょう。繰り返し同じフレーズを口にすることで、電話対応にも慣れて、フレーズが自然に口から出るようになります。
なお電話対応に使えるフレーズは、以下の記事でも紹介しています。詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。

【対策3】メモテンプレートの活用
メモテンプレートも、電話恐怖症の対策として活用できます。メモテンプレートを見れば何を聞けばいいのかが明確なので、通話中に重要なポイントを記録するための助けとして機能します。
またメモテンプレートを活用すれば、重要な情報を整理しやすくなるので、電話の後で内容を確認する際の安心感も得ることができます。
ちなみにメモテンプレートには、以下の項目を含めるのがおすすめです。
- 伝えるべき担当者の名前
- 電話を受けた日付と時間
- 伝言内容と対応が必要な期限
- 電話対応した人の名前
メモテンプレートを記載するときの注意点や、自社用にアレンジするための3つのアイデアなどについては以下の記事で詳しく紹介していますので、詳しく知りたい方はあわせてご覧ください。

【対策4】電話対応の研修
電話恐怖症の解決には、研修の実施もおすすめです。
研修を実施すると基本的な電話対応のスキルを鍛えられ「どのように対応したらいいんだろう」といった不安を軽減できるからです。
研修の内容としては、以下が主な流れとなります。
- 電話対応の基礎知識とスキルを学ぶ
- ロールプレイングで練習する
- 対応についてフィードバックを行う
とくにロールプレイングでの練習から得られるポジティブなフィードバックや成功体験は、日頃の顧客対応に関して自信を回復する助けにもなります。
電話対応の研修を実施する方法や、電話対応トレーニングで押さえるべき重要なスキルについては以下の記事で詳しく紹介しているので、ご一読ください。

【対策5】電話対応しやすい環境の整備
電話に対する恐怖を軽減するためには、電話対応がしやすい環境の整備も重要です。
- 電話対応を極力減らす
- 電話対応を強制しない
- 電話対応のミスを責めない
など「電話対応をしても怒られない」環境を用意して、電話対応がしやすいように整えましょう。
また、システムの導入も環境整備には有効です。
たとえばコミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」を導入すれば、着信時に顧客情報がポップアップされます。
電話相手の情報や自社の担当者、対応履歴を把握した状態で顧客と会話ができるので、「何を聞かれるんだろう?」「もし担当者がわからなかったらどうしよう」と心配になることがありません。
自動録音機能もついているので、聞き漏れなどのミスも予防でき「怒られるかもしれない」という恐怖心を軽減できます。
カイクラの詳細は以下から無料でダウンロード可能ですので、ぜひご確認ください。
\利用社数2,600社以上!/
カイクラの詳細を見る
▲無料ダウンロード資料あり
なぜ恐い?電話恐怖症につながる要因5つ

電話恐怖症につながる要因は、主に以下の5つがあげられます。
- 電話対応に対する自信のなさ
- 電話対応特有の言葉遣い
- 電話が聞き取れないことへの懸念
- 過去のネガティブな経験
- 相手がわからないことへの不安
電話恐怖症につながる要因を知ることで、恐怖心が生まれるきっかけへの理解が深まり、より効果的なサポートにつながります。
それでは、ひとつずつ紹介します。
【要因1】電話対応に対する自信のなさ
コミュニケーションの手段は変化しています。
以前までは電話が非対面における主なコミュニケーションの方法でした。しかしテキストでのコミュニケーションが一般化された現代では、「電話は緊急時に使われるツール」として認識している方も多いのではないでしょうか。
電話を利用する機会が減ったため、電話対応に自信が持てずに、いざ対応しようとしたときに恐怖や不安を感じてしまいます。
【要因2】電話対応特有の言葉遣い
電話対応には、電話対応特有の言葉遣いがあります。
「恐れ入りますが」「お差し支えなければ」など、日常生活では使い慣れない言葉が多いと感じる人も多いのではないでしょうか。
そのため「なんて言いかわからない」という不安が、恐怖心につながる恐れがあります。
【要因3】電話が聞き取れないことへの懸念
電話が聞き取れないことへの懸念も、恐怖心へつながる要因です。
電話は、さまざまな理由で聞き取るのが難しい場合があります。
▼聞き取るのが難しい場合
- 音質が悪い
- 周囲の音が大きい
- 話者が早口である
- 方言やアクセントが強い など
音が聞き取りづらい状況は、「通話中に重要な情報を逃すこと」への不安につながり、恐怖症へつながる要因となりえます。
【要因4】過去のネガティブな経験
「クレーマーによるストレス」など、過去のネガティブな経験も恐怖症の要因です。
電話で厳しい批判や理不尽なクレームを受けたり、大きな誤解を招いたりした経験があると、電話自体が不安や恐怖につながる恐れがあります。
社員の心身を守るためにも、クレーム対応についてのマニュアル作成やエスカレーション(責任者に対応を代わること)のタイミングを明確に定めましょう。
クレーム対策においては、以下の5点が重要です。
- まずは音声を録音する
- 基本の姿勢を崩さない
- 安易に相手の要求を呑まない
- 個人の連絡先を教えない
- 担当者1人で判断しない
クレーム対応のポイントやクレーム対応に役立つフレーズなどを詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

【要因5】相手がわからないことへの不安
電話では相手の顔が見えないため、相手の意図や感情を判断するのが難しくなります。
それに加えて「失礼な態度をとったらどうしよう」「自分にわからないことを聞かれないだろうか」のような不安や、相手がどのような人物であるか予測がつかないことも電話に対する恐怖心へとつながっています。
「電話相手がわからない」ということは、確認すべきことが多くコミュニケーションもとりづらいため、心理的負担になる要因です。
それでは「電話相手がわからない」にはどのように対応したらよいのでしょうか。ここからは、社員の心理的負担を軽減するコミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」を紹介します。
電話恐怖症の対策には顔がわかる「カイクラ」がおすすめ
電話対応における心理的負担の軽減に効果的なのは、コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」です。カイクラなら着信時に電話相手の情報がポップアップ表示されるので、お客様の写真や購入商品の画像を登録をすれば誰からの電話かが明確です。

また、名前や自社担当者、顧客の電話番号、対応履歴を確認した状態で会話を進められるので、「自社の担当者がわからなかったらどうしよう」「電話番号など必要な情報を聞き漏らさないか心配」といった不安も軽減できます。
「カイクラ」を導入すれば、電話に対して恐怖心がある方でも、安心して電話対応ができる環境作りが可能です。
カイクラの詳細は以下からダウンロードいただけますので、気になる方はご一読ください。
\利用社数2,600社以上!/
カイクラの詳細を見る
▲無料ダウンロード資料あり
電話恐怖症の解決は必須!会社が放置するデメリット

電話恐怖症の解決をおろそかにしていると、電話業務の妨げになります。なぜなら、職場から電話がなくなる可能性は低いからです。
シンカが実施したアンケートによると、「重要な話が会社の固定電話にかかってきたことはありますか?」という質問への回答は下記の通りです。
▼重要な話が会社の固定電話にかかってきたがことがあるか
頻繁にある:14.0%
たまにある:44.5%
めったにない(来たことはある):31.0%
まったくない:10.4%
このアンケートからもわかるように、業務に関与した重要な話が電話にかかってくる経験をしている社員は多くいます。
今後も電話業務がなくなる可能性は低いでしょう。
「電話が怖い」という気持ちは、離職につながる恐れもあります。電話業務がなくなる可能性が低いなら、電話業務を避けることはできません。
社員の離職を防ぐためにも、電話が怖いという社員のサポートは大切です。
まとめ:電話恐怖症を対策して電話対応の品質向上を目指そう!

電話対応は、会社の印象を決める大切な業務です。
しかし社員の中に電話に対する恐怖心がある場合、自信のなさから消極的で聞きづらいなど顧客にマイナスの印象を与える恐れもあります。
電話に対する恐怖心の克服は、仕組み化や周囲のサポートを必要とすることが多く、本人の努力だけでは難しい場合がほとんどです。
電話対応の品質向上のためにも、電話に恐怖を感じている社員がいた場合には、組織単位で対策やサポートをしていきましょう。
「システムの導入など仕組みからの改善が難しい」という方におすすめなのが、マニュアルの導入です。
多用するフレーズや電話対応の流れが記載してあるマニュアルが手元にあるだけで、いうべきことに詰まったときでも確認でき進めることができるので不安を軽減できます。
お手に取っていただいたらすぐにお使いいただけますので、「今すぐ使えるマニュアルが欲しい」という方は、ぜひ以下のリンクからダウンロードの上ご活用ください。
\明日から使えて電話対応時間を削減!/
カイクラの電話対応マニュアルをチェック
▲無料ダウンロードはこちらから