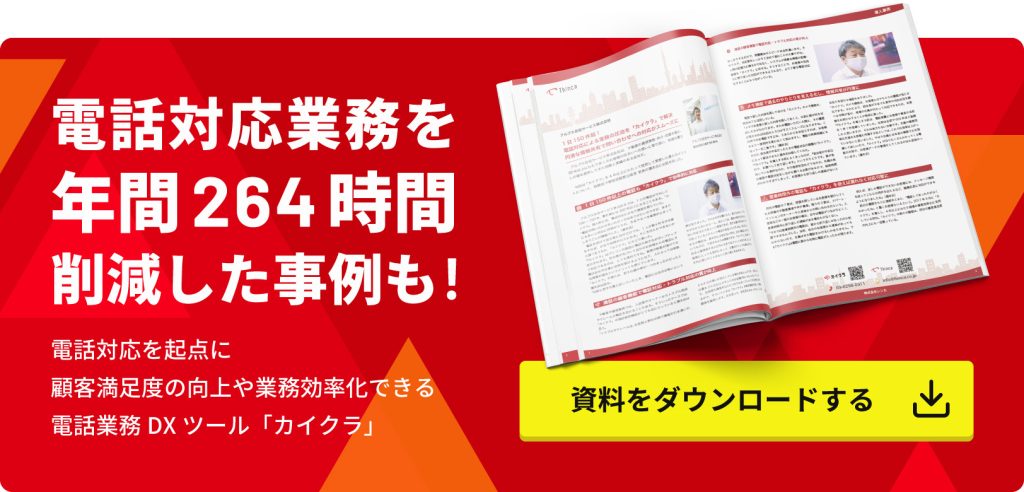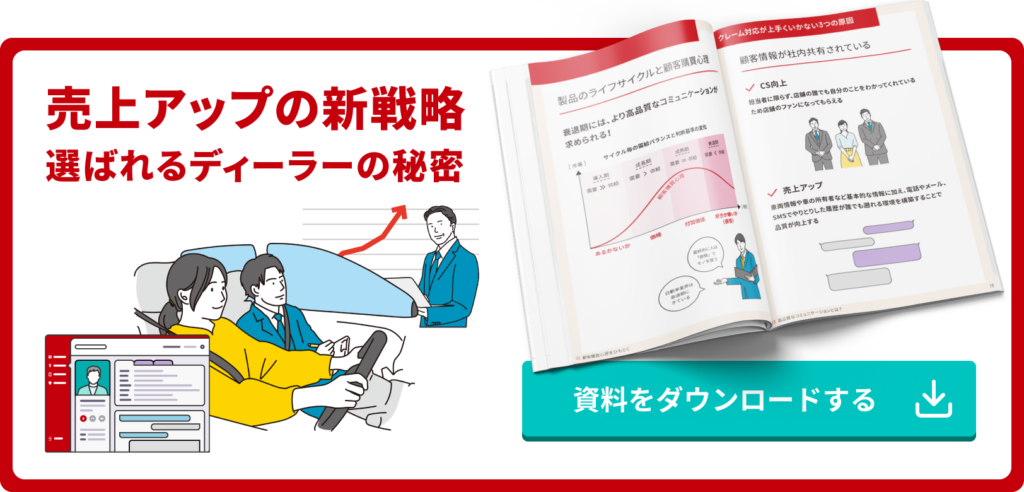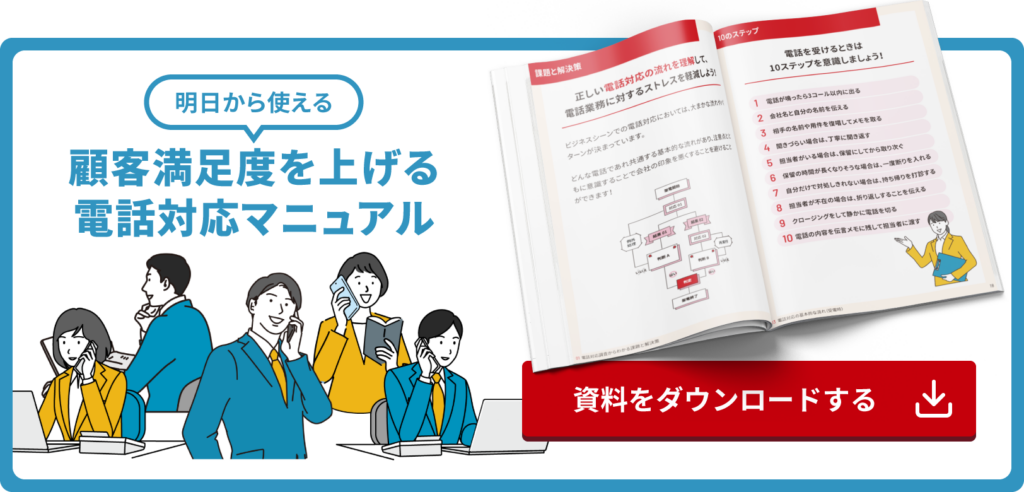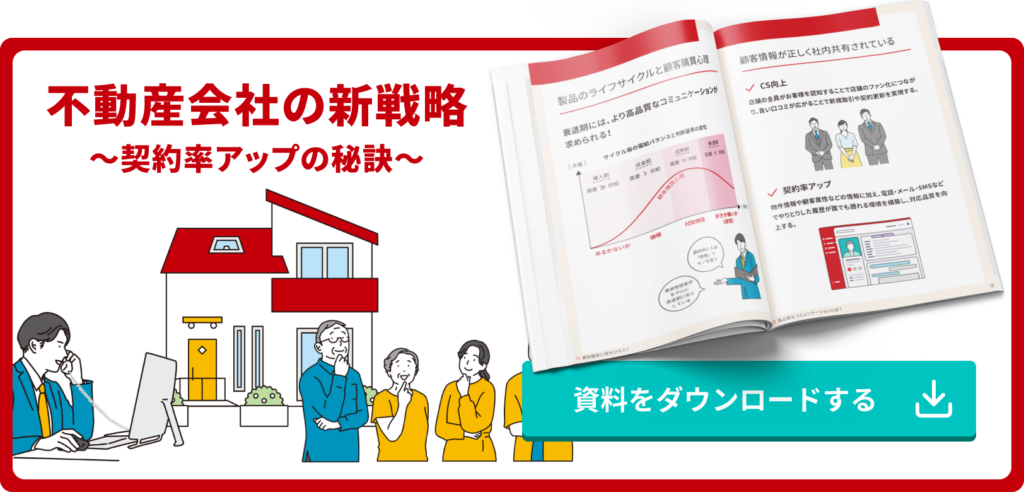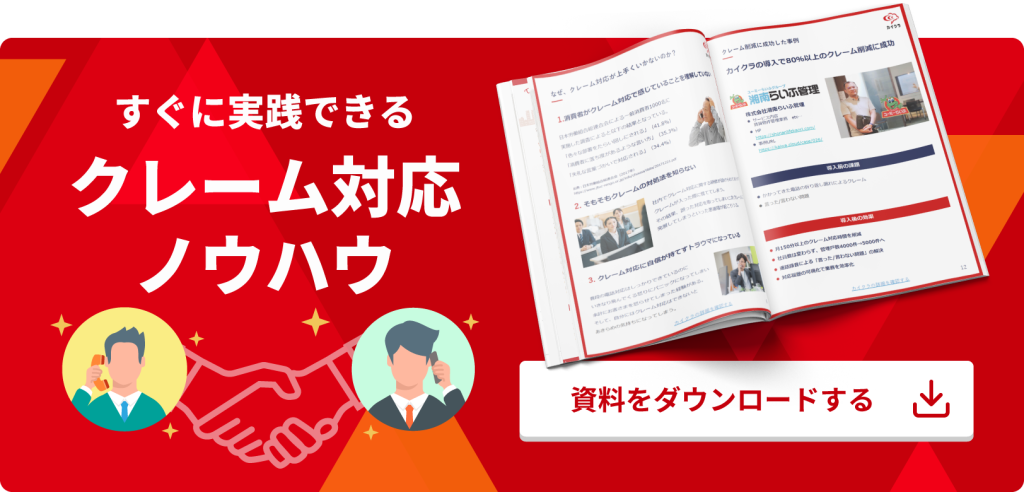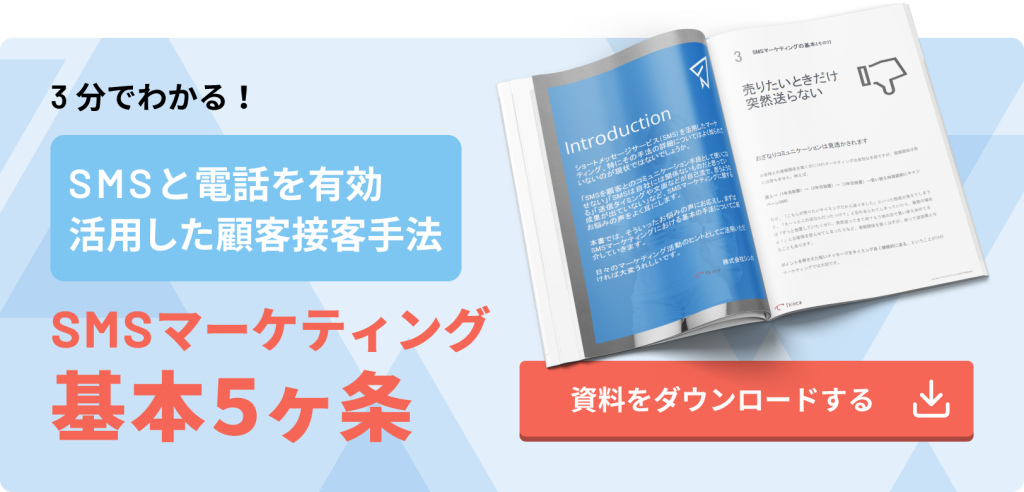カスハラ(カスタマーハラスメント)とは、顧客から従業員に対する理不尽なクレームや言動のことです。近年、こうしたハラスメントに悩む企業が増えており、とくに接客業務に従事する従業員が被害に遭うケースが多くあります。
企業がカスハラに対して適切な対策をおこなうことは、従業員の安全と精神的健康を守るために大切です。本記事では、カスハラに対して企業がとるべき具体的な対策を紹介します。
カスハラに対応するためには、世の中の動きや事例を知っておくことも大切です。カイクラでは、カスハラの事例や種類、クレームとの違いなどがわかる社労士監修のお役立ち資料を用意しています。
企業が講じるべき対策もまとめていますので、下記より無料ダウンロードしてご活用ください。
\社労士が監修!/
カスハラ対策の資料をダウンロード
▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説
カスハラ対策をする前に定義を確認!

まず、カスハラ対策をする前に定義を確認しておきましょう。以下の4つの項目に分けてカスハラの解説をします。
- 厚生労働省のカスハラの定義
- カスハラとクレームの違い
- カスハラの具体例
- カスハラが増えている背景
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.厚生労働省のカスハラの定義
カスハラがどのような行為のことなのかは、厚生労働省が定義しています。
顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・能様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・能様により、労働者の就業環境が害されるもの
暴言や暴力だけではなく、長時間の拘束や執拗なクレームなどもカスハラに該当します。
カスハラの定義は以下の記事で詳しく紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。

2.カスハラとクレームの違い
カスハラとクレームは似ているようですが違いがあります。たとえば、自社に何か過失があり、顧客の主張が妥当なものの場合は、カスハラではなくクレームです。
ただし、先ほどの定義にもあるように主張内容に正当性があっても、暴力や暴言などがあればカスハラに該当します。
カスハラかクレームを見分ける際は、まず主張内容に正当性があるか確認しましょう。もし正当性があっても、暴言や暴力、長時間の拘束、無理な要求がある場合はカスハラと捉えられます。
以下の記事ではカスハラとクレームの違いを解説しています。

3.カスハラの具体例
カスハラに対して適切な対策をするためには、まずどのような言動がカスハラに該当するのかを把握しておく必要があります。
厚生労働省のガイドラインでは、カスハラを「業務上、通常許容される範囲を超えた言動」と定義しています。なかでも、以下の表にまとめた精神的・身体的・性的な攻撃や、継続的・拘束的な言動がカスハラに該当する典型例です。
以下の表では、代表的な5つのパターンに分類し、それぞれの具体例をまとめています。
| 区分 | 具体例 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|
| 精神的な攻撃 |
|
威圧的な態度や人格否定。業務の範囲を超える発言が繰り返される |
| 身体的な攻撃 |
|
身体や物に対して暴力的な行動。従業員の安全が脅かされる |
| 性的な言動 |
|
不適切な発言・接触。セクハラとしての側面も |
| 継続・執拗な言動 |
|
正当な苦情の範囲を超えた粘着的な行動 |
| 拘束的な言動 |
|
従業員の時間や行動の自由を不当に制限 |
このように、単なる不満の表明とは異なり、相手の権利や人格を著しく侵害するような行為は、すべてカスハラに該当します。
とくに、現場の従業員は「どこまでが正当なクレームで、どこからがハラスメントか」の判断に悩むことが多いため、こうした具体例を共有しておくことが対策の第一歩です。
より詳しい業種別の事例や、対応マニュアルに活用できる事例は、以下の記事でも紹介しています。

4.カスハラが増えている背景
カスハラが増加している背景には、社会環境や技術の発展が関係しています。具体的な理由を以下の表にまとめました。
- 顧客側も企業に対する意見などを気軽に発言できるようになった
- 匿名性が高いので誹謗中傷が生まれやすい状況になっている
| SNSの普及と顧客の意見の発信の容易さ |
|
|---|---|
| 過剰なサービス競争と顧客の時代 |
|
これらの要因が複雑に絡み合い、カスハラの増加につながっていると考えられます。
カスハラ対策を放置することで起こるリスクとは?

企業にとってカスハラ対策をしないと起こるリスクを紹介します。
- 従業員の心身への影響と離職リスク
- サービス品質や顧客満足度への影響
- 企業ブランドや法的責任への波及
とくに、従業員はカスハラの影響を受けやすい立場です。それぞれどのようなリスクがあるのか、詳しくみていきましょう。
1.従業員の心身への影響と離職リスク
まずは、従業員への影響を配慮する必要があります。従業員はカスハラの被害の当事者になりやすく、実際に暴力や暴言を受ける可能性が一番高いからです。
カスハラがきっかけとなり、退職につながるケースも考えられます。
そのため、従業員が殴る蹴るなどの暴行を受けることがないように、まずは安全の確保が大切です。また、暴言などにより精神面に影響がないように配慮する必要もあります。
さらに、SNSへの投稿がきっかけとなる個人情報の流出にも注意が必要です。個人情報が流出してしまうと、ストーカー被害などのリスクも高まります。
従業員を守るためには、名札にフルネームを記載しない、ビジネスネームを使うなどの対策が必須です。
実際にカスハラが起きた際の対策としては、上司が対応を代わる・内容によっては警察に連絡するなどが挙げられます。
2.サービス品質や顧客満足度への影響
カスハラは、他の顧客への影響にも配慮しなければいけません。
たとえば、店内で従業員に対して暴言を言っている顧客がいると、他の顧客も怖がってしまったり不快に思ってしまったりする可能性が高いです。また、カスハラへの対応で業務が遅れることにより、他の顧客への対応が後回しになってしまいます。
加えて、カスハラに対して適切に処理できない現場に居合わせた顧客が「多少の無理難題でも押せば要求を飲んでくれる」と思ってしまい、カスハラを誘発してしまうことも避けなければなりません。
3.企業ブランドや法的責任への波及
カスハラと聞くと、暴言や暴力を想像する人が多いのではないでしょうか。しかし、それだけではありません。インターネットやSNSで企業のイメージダウンにつながる書き込みをされる可能性もあるからです。
また、悪質なカスハラが続くと、対応に疲弊した従業員が離職してしまう恐れもあります。従業員の離職も企業にとっては、大きな損失です。
企業は法律の観点からもカスハラに対策をしなければいけません。たとえば、労働契約法5条:従業員への安全配慮義務には、企業は従業員の安全を確保する義務があることが記されています。仮にカスハラ対策を怠った場合には、従業員から損害賠償請求されかねません。
イメージダウンや、従業員の離職を避けるためにも、カスハラへの対策が必要となります。
以下の記事では、カスハラに関連する法律の最新の動向を紹介しています。

企業が今すぐ始めるべきカスハラ対策7選

ここからは、企業がおこなうべきカスハラ対策を7つ紹介します。
- カスハラ対策マニュアルを作成する
- マニュアルに基づいて社員研修をおこなう
- クレームとハラスメントを区別できる基準を決める
- カスハラに対応できる体制を整える
- 従業員の安全を確保できる体制を作る
- 当時の状況を確認できる環境を整える
- 専門家に連携できる体制を作る
それぞれ順番に詳しく紹介します。
1.カスハラ対策マニュアルを作成する
まずは、カスハラが起きたときにどのように対応すればいいのか、企業が指針を示すことが大切です。対応を従業員に任せていては、企業として一貫した対処ができません。
そのため、カスハラへの対策を全従業員で共有できるよう、マニュアルを作成しましょう。
マニュアルには、以下の内容を盛り込みます。
| 基本的な方針や姿勢 | 組織としてカスハラ対策にどのように取り組むか基本的な方針や姿勢 |
|---|---|
| 相談・報告先 | カスハラを受けた場合の相談先・報告先 |
| 現場での初期対応 | 実際に現場でカスハラが起きた際の具体的な対応 |
マニュアルを作ることで、カスハラに対してすぐ適切な対処ができるわけではありません。しかし、事前にマニュアルを読んでおくことで、ある程度の対応ができるようになります。
また、カスハラに対する姿勢を明確にすることは、従業員が安心して働く環境づくりの一環になります。
マニュアルの作り方や具体的な内容は下記の記事で紹介していますので、あわせてご覧ください。

2.マニュアルに基づいて社員研修をおこなう
マニュアルの作成は大切ですが、マニュアルを作成しただけでは対策として十分ではありません。
実際にマニュアルをもとに従業員に対策の内容を周知させます。適宜社員研修をおこない、具体的な対策方法を伝えるようにしましょう。
自社で社員研修をおこなうリソースがない場合でも、厚生労働省の動画をみたり、eラーニングなどの教材を使って研修する方法もあります。自社のリソースにあわせて無理のない範囲で、社員研修をおこないましょう。
また、上司や現場監督者など、階層別に対策の研修をおこなうことも大切です。

3.クレームとカスハラを区別できる基準を決める
カスハラ対策を進めるうえで欠かせないのが、「どこまでがクレームで、どこからがカスハラか」を明確に線引きすることです。
対応の判断が曖昧なままでは、現場ではすべてをクレームとして処理してしまい、理不尽な要求や暴言にも応じることになりかねません。反対に、サービス改善のきっかけとなるクレームをカスハラとして対処してしまうこともあるでしょう。
こうした事態を防ぐためには、事前にクレームとカスハラを区別する基準を定め、対応ルールとして共有しておくことが重要です。
たとえば、「商品の不具合の説明を求める」などの内容であればクレームとして受け止めるべきですが、それが「この店は終わってる」「お前の顔をネットに晒してやる」などの暴言や脅しを伴うようであれば、カスハラとして対応を切り替える必要があります。
また、「ここまでは通常の苦情として対応し、それ以上の要求には応じない」など基準をマニュアルに明記しておくと、現場の迷いを防ぐことができます。
4.カスハラに対応できる体制を整える
実際にカスハラを受けたとき、従業員がすぐに相談できる体制を整えましょう。まずは上司にすぐに報告できる環境と対応が必要です。
そのほか、カスハラの相談や実際の対策をおこなうチームを設置します。対策チームでは、実際に起きたカスハラへの対応のほか、事例を作成したり再発防止策を考えたりします。
加えて、自社だけでは対応できない場合の相談先を確保することも大切です。警察や弁護士など、相談先の連絡先をおさえておきましょう。
5.従業員の安全を確保できる体制を作る
カスハラのなかでも、殴る蹴るなどの暴力行為やセクハラ行為がある場合、従業員の安全確保が必要です。具体的には、現場で上司が対応を代わったり、状況によっては警察に連絡したりします。
まずは、安全を確保することが最優先事項です。安全確保は、研修でも伝えておくべき内容となります。
また、顧客からの言動が理由でメンタルヘルスに不調がある場合には、産業医やカウンセラーへの相談など、企業としてアフターケアをおこなうようにしてください。
6.当時の状況を確認できる環境を整える
カスハラでは、防犯カメラの録画や電話の録音などで理不尽な要求かどうか確認できる場合があります。そのため、なるべくあとから確認できる環境を整えることが大切です。
また、防犯カメラや電話の録音は、カスハラを起こす人の抑止力にもつながります。たとえば、電話対応の場合には事前アナウンスとして「この通話はサービス向上のために録音させていただきます」などの音声が流れるようにしておくと、相手にも通話が録音されていることが伝わるからです。
自動通話録音機能も搭載されているのが、コミュニケーションプラットフォームのカイクラです。毎回、録音ボタンを押す必要はなく、自動で録音させるので、実際にカスハラが起きた場合にも録音漏れがなく、後から通話内容の確認ができます。
カスハラ対策をお考えの方は、以下よりお気軽にご確認ください。
\電話対応の負担が減ったとの声多数!/
カイクラの通話録音機能をチェック
▲無料ダウンロード資料あり
7.専門家に連携できる体制を作る
どれだけ社内で対策を整えていても、一企業の力だけでは対応しきれないカスハラ事案は存在します。たとえば、暴力的な発言や違法性が疑われる言動などは、企業内の判断だけでは適切な対処が難しくなるケースも少なくありません。
そのため、あらかじめ警察や弁護士など外部の専門家と連携できる体制を整えておくことが重要です。
体制が整っていれば、従業員が現場で過剰なプレッシャーを受けることなく、「これは社外に頼るべき案件だ」と判断したときに速やかに動けます。
また、カスハラ加害者側への抑止力にもなり、「会社は適切に対応する姿勢をとっている」と示すことで、悪質な行為の再発を防止する効果も期待できます。自社内だけで抱え込むのではなく、法的・公共的な支援と連携したカスハラ対策体制を構築するようにしましょう。
企業がカスハラ対策をおこなうメリット3つ

カスハラ対策は、従業員を守るだけではなく、企業にも多くのメリットがあります。カスハラ対策をおこなえば、以下のメリットがあります。
- 生産性の向上
- 従業員満足度の向上と定着率の改善
- ブランドイメージの向上
この章では、企業がカスハラ対策をおこなうことによって得られる3つのメリットを紹介します。
1.生産性の向上
カスハラ対策を適切に実施し、従業員がストレスなく快適な環境で働けると、生産性向上につながります。
なぜなら、不当な要求や過剰な対応時間がなくなることで、従業員は本来の業務に集中できるようになるからです。
その結果、業務効率が上がり、生産性の向上につながります。
2.従業員満足度の向上と定着率の改善
カスハラへの対策がとられている職場では、従業員も「自分たちは守られている」と安心感を持てます。
この安心感から従業員の満足度アップにつながり、結果的に働きやすい職場であると、モチベーションも高まり定着率の改善にも効果的です。
従業員の定着率が向上すれば、採用コストの削減や人材育成の効率化にもつながり、企業にとって大きなメリットとなります。
3.ブランドイメージの向上
カスハラ対策をしっかりとおこなっている企業は、「従業員を大切にする企業」として、社会的に高く評価されます。
その結果、ブランドイメージの向上に貢献し、求職者へのアピールにもなり、顧客からの信頼獲得にもつながります。良い人材を獲得しやすくなることは、企業の成長にとって非常に重要です。
カスハラ対策の成功事例と導入効果

カスハラは、単に「現場の努力」だけで防げるものではありません。企業全体で方針を示し、現場と連携した対策を継続的におこなうことが、実効性のあるカスハラ対策には欠かせません。
ここでは、実際に厚生労働省の事例集で紹介された企業の取り組みから、具体的な施策とその効果を紹介します。
- 店舗でのマニュアル共有と現場対応力の強化
- コールセンターでの苦情対応のマニュアルを強化
- SNSでのつきまとい行為から個人情報を守る対策を強化
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.店舗でのマニュアル共有と現場対応力の強化
株式会社イトーヨーカ堂様は、全国130店舗に共通のカスハラ対策マニュアルを配布し、トラブル発生時に即参照できるよう体制を整備しています。
本社のお客様相談部が基本方針を策定し、UAゼンセンや厚労省マニュアル、ACAP監修ハンドブックなどをもとに内容を構築しました。
とくに評価されたのは、マニュアルの一方通行ではなく、「現場の声を反映しながら随時改善する」運用姿勢です。
- 「2回以上同じ相手から発生した場合」の対応フローを明文化
- 店長・売場責任者・統括マネジャーなど役職別に階層別研修を実施
- 従業員には「マニュアルは道標であり、絶対解ではない」と明示し、柔軟な対応を推奨
このように、マニュアル+研修で現場の対応力を底上げした点が、制度の形骸化を防ぎました。
参考:厚生労働省カスハラ対策企業事例「株式会社イトーヨーカ堂」
2.コールセンターでの苦情対応のマニュアルを強化
ヤマト運輸株式会社様は、繰り返される暴言により、あるオペレーターが1か月の業務休止に追い込まれたことを契機に、経営層が「社員の健全な業務を守る」と明言します。カスハラ対策が全社レベルで本格始動しました。
- 「カスハラ発言リスト」や「対応文言集」を含めた実務用マニュアルを整備
- 研修による周知と、対応フローの習熟を徹底
- 対応レポートをデータベース化し、全社で共有・記録を蓄積
これにより、対応に悩んでいた社員が「自己責任で抱え込む」意識から解放され、「会社が守ってくれる」安心感と、毅然とした対応文化の浸透が実現しました。
3.SNSでのつきまとい行為から個人情報を守る対策を強化
タリーズコーヒージャパン株式会社様では、スタッフがSNSで検索・接触される事案が発生し、従来の対応では限界があると判断しました。本社がカスハラ対策の検討を開始し、ネームプレートの個人情報を見直す具体策を実施しました。
- フルネーム表記をやめ、イニシャル表示に変更
- 社内では誰が対応したか確認可能だが、外部には個人が特定されない仕様
- 「名前を知られて当然」の従来の発想を捨て、スタッフの安心感とリスク回避を両立
この対策により、SNSによるプライバシー侵害への抑止効果が高まり、スタッフの精神的な不安も軽減されました。
参考:厚生労働省カスハラ対策企業事例「タリーズコーヒージャパン株式会社」
これら3社の事例に共通するのは、マニュアルを「活きた仕組み」として運用し、従業員を守る姿勢を明確に示している点です。単なる形式的な取り組みではなく、現場が実感できる安心感や対応力向上につながっていることが、成功の鍵となっています。
業種別にみるカスハラの傾向と対応の工夫

カスハラ対策は業界共通の課題ですが、業種ごとに発生しやすいハラスメントの傾向や、適切な対応策は異なります。それぞれの業界で実際に起こっている事象に即した対策を講じることで、より実効性のあるカスハラ防止が可能です。
ここでは、以下の3つの業種を例に、それぞれの傾向と対応の工夫を紹介します。
- 飲食・接客業での対応ポイント
- 介護・医療業界での対応ポイント
- コールセンターでの対策ポイント
それぞれ詳しく解説します。
1.飲食・接客業での対応ポイント
飲食店や小売店舗は、店内での暴言や暴力、無償提供の要求など過剰なクレームが発生しやすい業種です。また、スタッフを名指しでSNSに晒す行為や、人格攻撃に発展するケースもみられます。
こうしたカスハラへの対応は以下が有効です。
- 名札にはイニシャルや役職名を記載して個人特定を防止する
- 録音・防犯カメラを設置して記録を残す
- クレーム対応マニュアルを整備し、店長・副店長が初動対応を徹底する
- 上司への報告基準を明確にし、現場判断の負担を軽減する
- 「迷惑行為は退店をお願いする」などの掲示物を設置し、抑止力を高める
これにより、スタッフの安心感を保ちつつ、毅然とした対応が可能になります。
2.介護・医療業界での対応ポイント
介護や医療現場では、患者やその家族からの暴言・暴力、職員への過干渉が問題になっています。「あの職員を外せ」などの要求や、治療・介護方針への執拗な介入も発生する可能性があります。
対応例は下記のとおりです。
- 全職員にカスハラ対応フローを共有し、迷わず対応できる体制を整備する
- 名札は役職・苗字までに限定し、プライバシーを保護する
- 1人では対応せず、必ず複数名での応対を基本とする
- 日誌や会話ログを残し、客観的な事実を記録する
- 精神的負担が大きいため、メンタルケアの仕組みを併設し継続的にサポートする
このような対応により、職員の安心感が保たれ、業務の質も安定します。
3.コールセンターでの対策ポイント
コールセンターでは、長時間の電話拘束、人格否定、管理職を出せなどの執拗な要求が起きるケースが散見されています。BtoBの取引先からは、優越的地位を利用したパワハラ的言動もなくなりません。
このような電話対応においては、下記の対策が必要です。
- 全通話を自動録音しつつ、録音アナウンスで抑止効果を狙う
- 「カスハラ発言リスト」や対応マニュアルを活用し、対応を標準化する
- カスハラだと思われる場合はすぐに管理者へ引き継ぐ
- 複数の担当者で情報を共有し、対応履歴を社内DBに記録する
- BtoB対応では、窓口の一本化や書面でのやり取りへ切り替える
対応を属人化させず、組織全体で守る体制が重要です。
今すぐできるカスハラ対策「通話録音」で従業員と会社を守る

先ほどの事例にもあったように、カスハラは対面だけで発生するわけではなく、電話対応でも被害を受けてしまう可能性があります。
対面でのカスハラは第三者が介入できるため、1人だけで対処せずに済むことが多いです。一方で、電話の場合は1対1での対応が基本となるため、対応者だけに任せない環境づくりが欠かせません。
そのため、ここからは電話対応でカスハラを受けた場合に有効なコミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」を紹介します。
電話でのカスハラ対策は通話録音が必須です。電話は一対一なので、相手が「そのようなことは言っていない」と主張すると事実がわからなくなる恐れもありますが、通話録音があれば後から聞き直して事実を確認できます。
たとえば「カイクラ」は自動録音機能があるので、カスハラと思われる発言があった場合に録音されていなかったという事態が発生しません。どの通話でも後から聞き直しができるうえ、証拠としても残るためトラブルに発展した際にも役立ちます。
自動録音していることが顧客にも伝われば、カスハラの抑止力としても効果的です。
また、受電時に誰からの電話かわかるので、何度もカスハラと思われる電話をかけてくる顧客に対して、はじめから上司が電話に出るなどの対処が可能になります。

▲顧客情報画面のイメージ
カイクラでは、カスハラ対策に役立つ資料も用意しております。カスハラ対策にお悩みの方は、お気軽に以下よりご確認ください。
\社労士が監修!/
カスハラ対策の資料をダウンロード
▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説
まとめ:カスハラ対策は企業の義務と考えよう!

大切な従業員やその他の顧客を守るためにも、カスハラ対策は企業にとって大切な仕事です。カスハラへの対策は、マニュアルを整備して対策する必要があります。
また、カスハラは対面だけではありません。電話対応でもカスハラを受ける恐れがあるため、電話対応マニュアルの整備も必要です。
カイクラでは、従業員を守るカスハラ対策のお役立ち資料を用意しております。社労士監修で、カスハラ防止をめぐる世の中の動きから事例、クレームとの違いも解説しています。
カスハラの対策を講じたいとお考えの方は、以下より無料でダウンロード可能ですので、お気軽にご確認ください。
\社労士が監修!/
カスハラ対策の資料をダウンロード
▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説