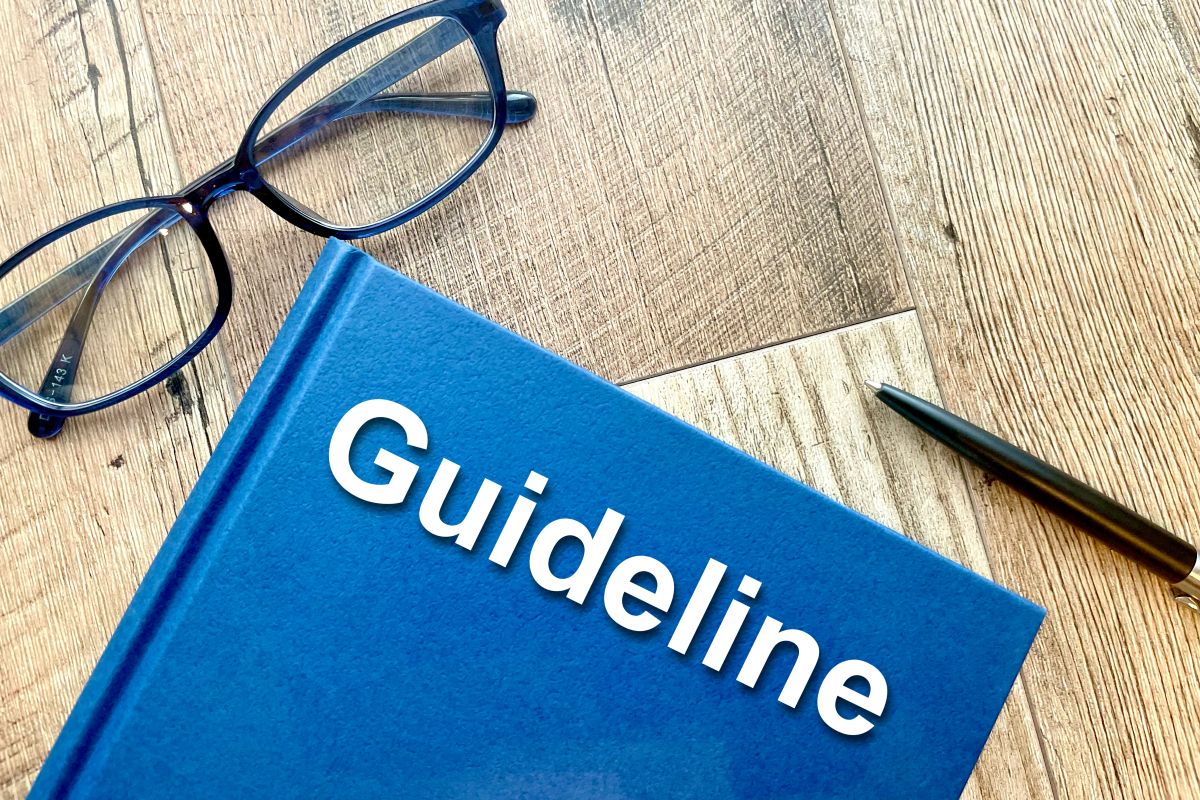カスハラ(カスタマーハラスメント)が社会問題となるなか、厚生労働省は企業が取り組むべき対策を定めたガイドラインを公表しました。しかし、「どこからがカスハラと判断されるのか」「通常のクレームとの違いは何か」「企業として具体的に何をすればよいのか」などの疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、厚生労働省が示すカスハラの基本をわかりやすく解説します。あわせて、指針の位置づけを整理し、企業が最低限整える必要のある「体制づくり」「社内規程(ルール)」「従業員研修」の要点を紹介します。
さらに、トラブル発生時の対応フローや、社内マニュアル・研修への落とし込み方も、すぐに実践できる形でまとめました。
カスタマーサクセス領域における業務改善のプロフェッショナル。株式会社シンカのマネージャーとして、3000社以上の「カイクラ」導入企業を支援するチームを統括。担当業務の多様化・複雑化に伴う「タスクの抜け漏れ」や「業務の属人化」といった、多くの企業が抱える課題に対し、ITツールを活用した業務プロセスの抜本的な再構築を主導。現場の課題解決から事業成長までを幅広く支援する、電話コミュニケーションDXのプロ。

「まず何から始めればいい?」と思っている方に向けて、カスハラ対策の基本を一冊にまとめた無料のお役立ち資料もご用意しています。社内の体制整備や研修計画づくりに、ぜひご活用ください。
\社労士が監修!/
カスハラ対策の資料をダウンロード
▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説
まず押さえておきたい厚生労働省が示すカスハラ定義

カスハラ対策を始めるにあたり、まずは厚生労働省が示すカスハラの定義や具体例を正しく理解することが大切です。ここでは、厚生労働省のガイドラインの内容を基に、以下の3つに分けて解説します。
- 厚生労働省のガイドライン概要
- 厚生労働省が示すカスハラの具体例
- カスハラとクレームの違い
それぞれ詳しくみていきましょう。
厚生労働省のガイドライン概要
厚生労働省は、2022年2月に「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」およびガイドラインを公表しました。これは、カスハラに対する企業の対応を統一・標準化し、現場任せや個人の判断に依存する状況を防ぐことを目的としています。
つまり、カスハラ対応を「属人的なもの」ではなく、「組織としての対応」に引き上げることが重要であると示しています。
厚生労働省が示すカスハラの具体例
厚生労働省は、カスハラを「顧客等からの不当な言動」と定めています。具体的には、以下の行為がカスハラに該当します。
- 暴行、傷害、脅迫、侮辱、名誉毀損などの身体的・精神的な攻撃
- 長時間居座る、土下座を要求する、金銭を要求する、不当な謝罪文の提出を求めるなどの不当な要求
- 同じ内容のクレームを何度も繰り返す、頻繁な電話やメールなどの繰り返しおこなわれる言動
- 人種や性別、障がいなどを理由にした差別的な発言
これらの行為は、従業員の安全を脅かし、心身の健康を損なう可能性があります。企業が適切に対応しない場合、従業員から損害賠償などの責任追及を受ける可能性もあるため、適切な対応が必要です。
参考:カスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成事業検討委員会
どのような行為がカスハラに該当するのかさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご確認ください。

カスハラとクレームの違い
正当なクレームとは、商品やサービスに不備があった場合に、その改善や謝罪を求めるなど、社会通念上の妥当性がある要求を指します。一方、カスハラは、要求の内容や手段が社会通念上の妥当性を欠く行動です。
たとえば、「購入した商品がすぐに壊れてしまったので交換してほしい」は正当なクレームです。しかし、その際に大声で怒鳴り続けたり、不必要な土下座を要求したりする行為は、カスハラに該当すると考えられます。
正当なクレームであっても、その言い方、態度、回数などがエスカレートすると、カスハラに変わることがあります。判断のポイントは、その要求が「社会通念上の妥当性」があるかどうか、そして「従業員の安全」が脅かされていないかです。
カスハラかどうか判断が難しいときに備え、従業員がいつでも相談できる体制を事前に整えておくことが大切です。
カスハラとクレームの違いを具体的な事例を交えてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

カスハラ対策は企業の義務?厚労省の指針と法改正の最新動向

「カスハラ対策は企業にとって努力目標であり、罰則はないのでは?」と考える方もいるのではないでしょうか。しかし、法改正の動きや厚労省の指針を確認すると、カスハラ対策はもはや「やっておけばよい」ではなくなっています。
ここでは、以下の3つに分けて最新動向を解説します。
- 厚生労働省の指針
- 法改正で変わる義務化の有無
- 企業に求められるカスハラ対策への措置
とくに法改正で変わる義務化の有無は、最新の情報を確認するようにしましょう。それぞれ詳しく解説します。
1.厚生労働省の指針
厚生労働省は、2022年2月に「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成事業検討委員会」を策定しました。これは、企業が従業員を守るための体制整備や、具体的な対応方法の参考資料として活用されることを目的としています。
このマニュアルでは、社内ハラスメント(パワハラなど)との相違点を明確にしています。最も大きな違いは、加害者が「顧客等」である点です。外部からのハラスメントに対して、企業がどう従業員を守るべきか、具体的な対応策が示されています。
2.法改正で変わる義務化の有無
現在、厚生労働省が公表しているマニュアルは、あくまで企業が自主的に取り組むべき「指針」であり、直接的な罰則はありません。しかし、カスハラに対して企業が不適切な対応を取った場合、安全配慮義務違反として、従業員から損害賠償を求められるなどの法的リスクはあります。
さらに、今後の法改正によって、この状況は大きく変わろうとしています。2025年秋から2026年初頭を目安に、「労働施策総合推進法」の改正によって、カスハラ対策が法律で義務化される見込みです。これにより、これまで以上に企業の責任が明確になります。
法改正の詳しい内容や、企業が今から取るべき対応策は、以下の記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

3.企業に求められるカスハラ対策への措置
では、企業は具体的にどのような対策を講じる必要があるのでしょうか。厚生労働省のガイドラインや法改正の動向を踏まえると、以下の5つの措置がとくに重要とされています。
| 企業の方針の明確化 | カスハラを許さない企業の方針を明確にし、従業員に周知する |
|---|---|
| 相談体制の構築 | 従業員がカスハラの被害に遭った際に、安心して相談できる窓口や担当者を設ける |
| 記録と報告 | 発生したカスハラの状況を正確に記録し、組織内で共有する仕組みを作る |
| 被害者のケア | 被害に遭った従業員の心身の負担を軽減するためのケア体制を整える |
| 再発防止のプロセス | 再発防止のために、具体的な対策を講じる |
これらの対策は、厚生労働省だけではなく、関係省庁や業界団体が提供する啓発資料なども活用することで、より効果的に進められます。また、今後も法改正などで状況が変わる可能性があります。最新の情報を定期的にチェックするようにしましょう。
厚生労働省のガイドラインに準じた企業の対策

実際にガイドラインに沿ってどのような対策を進めていけばよいのでしょうか。企業が最低限講じるべき対策は、以下の3つです。
- 体制整備
- 対応マニュアルの整備
- カスハラ対応研修
それぞれ詳しく解説します。
1.体制整備
カスハラ対策を成功させるには、まず社内での体制整備が欠かせません。具体的には、以下の3つのポイントを押さえておくことが重要です。
- カスハラを許容しない基本方針の明確化
- 相談窓口と外部専門家につなぐルートの整備
- 記録体制の統一
まずは、「カスハラは許容しない」と企業の態度を社内外に示します。
その後、従業員が一人で抱え込まずに済むよう、社内の相談窓口を設置しましょう。必要に応じて弁護士などの外部専門家と連携できるルートを整備しておくと安心です。
カスハラが発生した際の体制として、日時、場所、内容などを正確に記録できるよう、カスハラ発生状況を記録するためのテンプレートを用意しておくことも必要になります。
とくに電話対応では、「言った言わない」のトラブルになりやすいため、通話録音の導入を検討するのがおすすめです。自動で録音できるツールなどを活用すれば、録音漏れもなく、後からいつでも確認できるため、客観的な証拠として活用できます。
カイクラは自動で通話録音ができるコミュニケーションプラットフォームです。録音漏れの心配もないカイクラの詳細を確認したい方は、以下よりご確認ください。
\電話対応の負担が減ったとの声多数!/
カイクラの通話録音機能をチェック
▲無料ダウンロード資料あり
2.対応マニュアルの整備
体制を整備した後は、具体的な対応手順を定めたマニュアルを整備しましょう。従業員一人ひとりが正しい判断基準と対応方法を共有することで、属人的な対応を防げます。
マニュアルには、カスハラの定義や代表例、そして具体的な対応手順を記載しましょう。「これはカスハラか、クレームか?」と判断に迷った場合に備えて、フローチャートなどを活用すると、よりわかりやすいマニュアルになります。
厚生労働省のガイドラインを活用して、マニュアルを作成する際の具体的なポイントは以下の記事で解説しています。

3.カスハラ対応研修
最後に、作成したマニュアルを現場で活かすために、カスハラ対応研修を実施しましょう。マニュアルを配布するだけでは、緊急時に従業員が冷静に対応することは難しいからです。
研修では、一般職と管理職で内容を分け、それぞれの立場に応じた適切な対応方法の研修をおこないます。また、ロールプレイングを取り入れて、実際のカスハラ場面を想定した練習をすることも効果的です。必要に応じて外部の専門機関が提供する研修を活用することも検討してみてください。
カスハラ対応研修の重要性や進め方は、以下の記事で詳しく解説しています。

厚生労働省のガイドラインを活用してマニュアルを作るポイント

対策をより効果的にするためには、ガイドラインの内容を自社のマニュアルに落とし込む必要があります。ここでは、マニュアルを作成する際の3つのポイントを詳しくみていきましょう。
- ガイドラインから取り入れる要素
- 使いやすいマニュアルづくり
- 職種にあった事例の収集
とくに実態にあわせたマニュアルを作るためには、職種にあった事例の収集が大切です。詳しくみていきましょう。
1.ガイドラインから取り入れる要素
厚生労働省のガイドラインには、企業がマニュアルに含めるべき重要な要素が記載されています。以下の3つの要素を、自社のマニュアルに必ず取り入れましょう。
- カスハラの定義と分類の明確化
- 基本方針・相談体制・対応フローの整備
- 教育・研修や社内共有のあり方
何がカスハラにあたるのか、暴言や不当な要求など具体的な分類を示す必要があります。このとき、自社で発生しやすいカスハラの具体例を明記しておくと、従業員がカスハラかどうか判断しやすいです。
また、カスハラへの毅然とした態度、相談窓口の存在、そして被害が発生した場合の具体的な対応手順を明記します。
さらに、マニュアルの内容を従業員に浸透させるための教育方法や、情報共有の仕組みも定めておきましょう。これらの要素を盛り込むことで、従業員が迷うことなく適切な対応を取れるようになります。
2.使いやすいマニュアルづくり
せっかくマニュアルを作成しても、使いづらいものでは意味がありません。緊急時に従業員がすぐに確認し、活用できるようなマニュアルを作成しましょう。
- 視覚的にわかりやすくする
- シンプルでわかりやすい内容にする
- すぐに確認できるように配布する
文字ばかりではなく、イラストやフローチャートを積極的に活用することで、内容が直感的に理解できるようになります。専門用語を避け、誰が読んでも理解できる言葉で記述しましょう。さらに、紙媒体で配布するなど、従業員がいつでも確認できるようにして置くことが大切です。
3.職種にあった事例の収集
カスハラは、業種や職種によって発生する内容が異なります。たとえば、小売業と医療機関では、想定されるカスハラの内容は大きく違います。
マニュアルの実用性を高めるためには、厚生労働省のガイドラインにある一般例だけではなく、なるべく自社で起きた事例や、同業他社で起きた事例を参考にすることが大切です。これにより、より実態にあったマニュアルを作成できます。
さまざまなカスハラ事例と、それに対する適切な対策方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ:厚生労働省のガイドラインに沿ってカスハラ対策をしよう

本記事では、厚生労働省のガイドラインを中心に、カスハラの定義や企業が取るべき対策を解説しました。
結論として、カスハラは個人で対応するものではなく、企業として組織的に対策を講じる必要があります。
従業員が安心して働ける環境を整備することは、企業の責務です。カスハラ対策を進めるためには、本記事で紹介したように、体制整備、マニュアル作成、研修など、やるべきことが明確にあります。
しかし、「何から手をつけたらいいかわからない」方もいるのではないでしょうか。そのような方のために、カスハラ対策のポイントをまとめたお役立ち資料をご用意しました。以下のフォームから無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
\社労士が監修!/
カスハラ対策の資料をダウンロード
▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説