昨今、カスハラ(カスタマーハラスメント)をめぐる訴訟が話題になることが増えてきました。
暴言や過度な要求など、従業員を苦しめる行為に対して毅然と対応し、顧客を訴える企業の事例も現れ始めています。一方で、カスハラへの対応を誤り、逆に従業員から訴えられる企業もあり、企業側には適切な判断と備えが求められています。
たとえば、株式会社しまむらは2024年8月「カスタマーハラスメント対応ポリシー」にて、カスハラ顧客を店舗などへの出入り禁止にする方針を発表しました。
顧客のニーズに寄り添うことは大切ですが、従業員の安全や尊厳を守ることも、企業にとって重要な責任です。問い合わせがクレームになり、更に発展してハラスメント化して訴訟に至るケースもあります。
そこで本記事では、カスハラを巡る訴訟の事例や、従業員をカスハラから守り、訴訟化の防止につながる施策を紹介します。
カスハラの予防策・訴訟対策として有用なのが、顧客コミュニケーションを円滑化するツールです。
カイクラの場合、やりとり履歴を一元的に管理するため状況確認がしやすく、コミュニケーションエラーを防げます。また通話が録音されるため、事実を証明するためにも効果的です。詳しくは以下よりご覧ください。
\利用社数3,000社以上!/
カイクラの詳細を見る
▲無料ダウンロード資料あり
カスハラは訴えられる?企業が対策を求められる事情
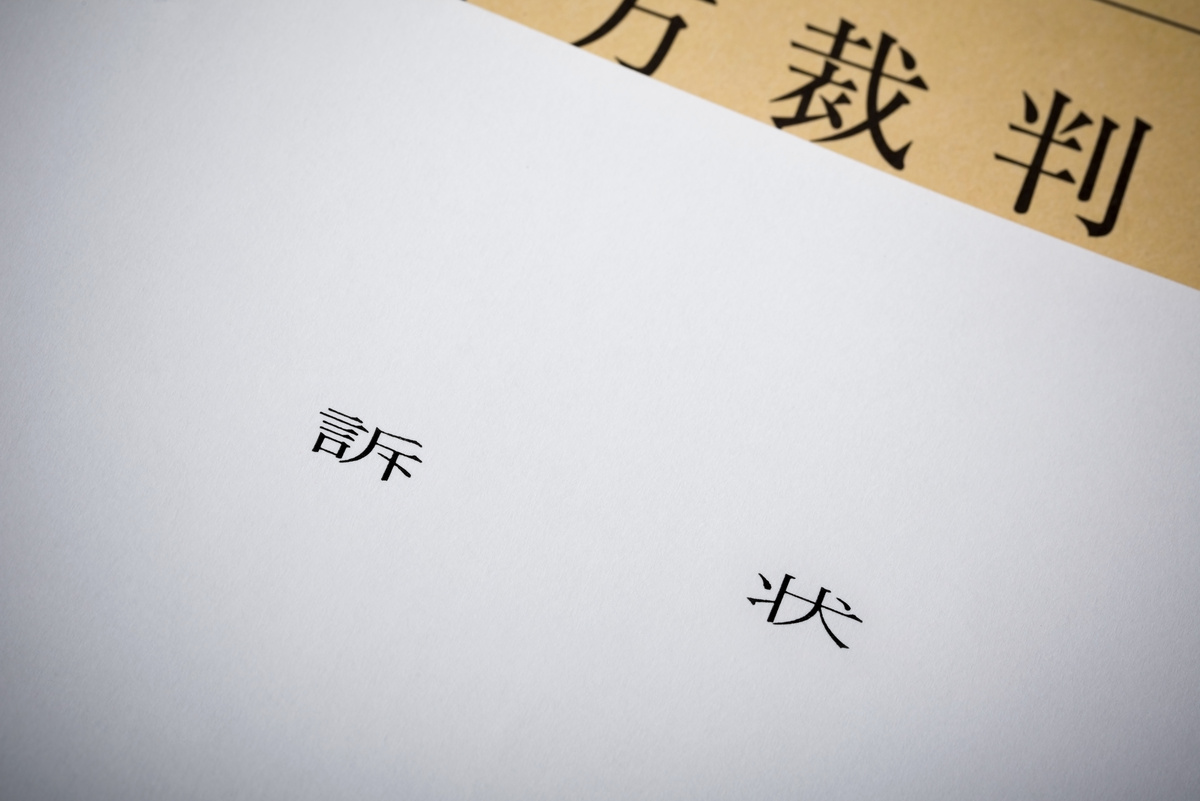
カスハラとはカスタマーハラスメントの略で、顧客による妥当性を欠いた要求やクレームのことを意味します。
具体的には、暴言や暴力、脅迫、中傷、侮辱、無理な要求や、SNSなどでの誹謗中傷などです。差別的・性的な言動や個人への攻撃も含まれます。
カスハラについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご一読ください。

カスハラは深刻な問題です。パーソル総合研究所「カスタマーハラスメントに関する定量調査」(2024年)によると、サービス系職種におけるカスハラ被害の経験率は、全体の35.5%でした。
調査時点から3年以内のカスハラ経験率は20.8%、離職率が高い職種は福祉職、ホテル宿泊業、受付・秘書などという結果も出ています。
カスハラが稀な問題ではないことが伺えるなか、行政はカスハラ対策に乗り出しました。2025年4月、東京都や群馬県、北海道では「カスタマーハラスメント防止条例」が施行され、対策が推進されています。
カスハラ防止条例に関しては、以下の記事もあわせてご確認ください。

カスハラ訴訟のパターンは大きく3つ

カスハラが原因で訴訟になる場合、原告が誰になるかによって3つのパターンがあります。
- 企業が顧客を訴える
- 従業員が企業を訴える
- 企業が顧客企業を訴える
まずは、企業が原告となって顧客を訴えるパターンです。威力業務妨害罪、強要罪、脅迫罪、名誉毀損罪などがあります。
次にカスハラ被害にあった従業員が原告となり、職場企業に対して「安全配慮義務違反」を問うパターンです。労働契約法第5条にある通り、企業は従業員が安全かつ健康に働けるよう配慮し、 心身の健康を害さないよう対処しなければなりません。
しかし、顧客の言動に適切な対処を施さなかったという理由で法律違反となり、従業員から訴えられるケースが実際に発生しています。
最後は、企業間において取引相手を訴えるパターンです。ものやサービスの提供側とそれを受ける顧客の関係が成り立つ場合、妥当性のない要求や暴言などを理由にカスハラ訴訟に至ることがあります。
以上のように訴訟パターンをみてきましたが、イメージしにくい方のために、続いてそれぞれの訴訟事例を紹介します。
カスハラを訴えられた事例5つ

本章では、カスハラを原因とした訴訟事例を5つ紹介します。
- 自治体が住民を訴えた事例
- 衣料品店が顧客を訴えた事例
- コールセンターが従業員に訴えられた事例
- 病院が看護士に訴えられた事例
- 企業が取引相手に訴えられた事例
ぜひ参考にしてください。
1.自治体が住民を訴えた事例
1つ目は、大阪市による住民への損害賠償請求事例を紹介します。
自治体の窓口では住民が職員に対し、過度な要求をするケースが少なくありません。大阪市ではその住民が職員に暴言や1日に9回もの電話、情報公開請求を50回以上、職員への暴言をおこなっていたそうです。
特定の職員に対する執拗な要求と罵倒および、差別的発言や脅迫の差し止めと損害賠償を求めた裁判では、大阪市が勝訴しました。
参考:カスタマーハラスメント(カスハラ)の対応方法について、弁護士が事例を踏まえて解説
2.衣料品店が顧客を訴えた事例
2つ目は、2013年に衣料品店「ファッションセンターしまむら」で起きたカスハラ訴訟の事例です。「タオルに穴が開いていた」としてクレームで訪れた女性客が、店員に謝罪と返品・返金と交通費を要求しました。
店員は交通費を払えない旨を伝えましたが、その女性客は引き下がることなく、土下座を強要したそうです。店員は結局土下座をしましたが、女性はその様子を撮影し、実名とともにSNSに店の悪評を投稿してしまいました。
顧客の度を超えた行動に、店舗側は警察に被害届を出すに至っています。裁判では名誉棄損罪が認められました。
参考:『しまむら』店員に土下座を強要した女性が略式起訴となった事件について
3.コールセンターが従業員に訴えられた事例
3つ目は、コールセンターの運営企業が社内から訴えられた事例です。顧客からカスハラ被害を受けた従業員が、職場であるNHKサービスセンターの対応方針の不備を理由に損害賠償責任を問う訴訟を起こしました。
しかし、同社は顧客対応におけるカスハラ対策が整っていたため、安全配慮義務違反を認められることはありませんでした。
4.病院が看護士に訴えられた事例
4つ目は、医療機関が看護士から訴えられた事例です。入院患者から暴行を受けた看護士が、安全配慮義務違反を理由に病院に対して損害賠償請求をしました。
原告側の看護士は、入院患者から障害が残るほどの暴行を受けたため、看護士としてできる業務範囲が狭まってしまっていました。そしてこのことは現在だけではなく、看護士の生涯にわたる労働力の損失を意味します。
判決では、病院側の安全配慮義務違反が認められ、損害賠償と慰謝料の支払いが命じられました。
5.企業が取引相手に訴えられた事例
5つ目は、自社の従業員が抑うつ状態になったなどの理由で、東京都の住宅設備販売会社が取引先2社を訴えた事例です。
原告側の企業は、従業員が被告側企業で約2時間にもわたって怒声や罵声を浴びせられて抑うつ状態になり、休職につながったとして計1,100万円の損害賠償を求めました。
その一方で訴えられた企業はカスハラ行為を否定し、事実関係を巡る裁判となりました。
参考:取引先からのカスハラ訴訟、訴えられた企業は「強く否認」 札幌地裁
カスハラ訴訟を防ぐためにすべきこと3つ

カスハラ訴訟事例をみてきましたが、訴訟を防ぐためにはどのような対策があるのでしょうか?
カスハラ訴訟の防止策を3つ紹介します。
- 対応方針を整え、社内研修で教育する
- カスハラの相談体制を構築し、配慮を欠かさない
- 顧客対応の現場を記録する
これらは、企業のコンプライアンス遵守にもつながる施策です。自社の状況と照らし合わせながら、参考にしてください。
1.対応方針を整え、社内研修で教育する
まずは、カスハラの定義を明確にし、対応方針とマニュアルを作成して周知しましょう。
どのような行為がカスハラの範囲にあたるのかを、明確に把握していない場合が少なくありません。顧客対応における妥当な要求の範囲とカスハラにあたる範囲を明示します。
そして、当てはまる言動に対する具体的なアクション基準を設定することで、いざというときに遅れなく対処することが可能です。また、社内研修などで規定通りの対応ができるように教育することも大切です。
2.カスハラの相談体制を構築し、配慮を欠かさない
続いての防止策は、経営層や管理職が中心となり、従業員のフォロー体制を整えることです。万が一カスハラがあった際には、上司やメンターが従業員に寄り添い、相談を実施しながら早急に対処できるようにします。
そして、従業員が精神的に高いストレスを受けている場合は産業医による面談に引き継ぐことも検討しましょう。
ちなみに従業員数が50人未満の小規模事業者の場合、地域産業保健センターで産業保健サービスを無料で受けられます。
3.顧客対応の現場を記録する
店舗の場合、防犯カメラを設置するなどして顧客と従業員との接点を記録するシステムを構築することもトラブル防止に役立ちます。現場を記録することで、カスハラ事案が発生した際の証拠になるからです。
顧客対応に電話を利用している場合も、同様に通話録音がカスハラ訴訟の防止策となります。通話録音は、カスハラが発生した際、第三者が事実確認するための材料になるためです。
「カイクラ」で実現するカスハラ防止策

前章でも触れた通り、通話録音はカスハラに限らず、顧客や取引先との間にトラブルが発生した際に役立ちます。通話を録音する方法はいくつかありますが、自動で録音できるツールを活用すると確実に記録できるため便利です。
たとえばカイクラの場合、普段から顧客対応履歴と内容が自動で記録されるため録音漏れがないうえ、業務の効率化も期待できます。
実際、トラブル対応に効果を実感した企業が少なくありません。参考までにカイクラの導入事例を2つ紹介します。
1.株式会社ネクサスエージェント様

不動産業やコンサルティング業を営む株式会社ネクサスエージェント様は、多種多様な用件で日常的に電話を使用しています。
営業社員の電話においては社用携帯の録音機能を使用していましたが、手動で録音ボタンを押さなければならず、押し忘れるなどの運用面での不安がありました。
すべての通話を確実に録音でき、利便性の高いサービスを探していたところ、カイクラの通話録音機能にいきついたといいます。確実に通話を記録できることで顧客との間にトラブルが発生しても、迅速に対応できるようになりました。
その結果、迅速な対応が可能になり、該当事案のトラブル化を防げています。また、同社では通話録音データが社員教育にも活かされています。客観的な事実にもとづいた対応記録をもとに、具体的な顧客対応指導ができるようになったそうです。
2.株式会社駐車場をさがせ様

駐車場の管理運営をおこなう株式会社駐車場をさがせ様は、日々顧客とは電話でのやりとりが多く、顧客を待たせてしまうことが課題でした。
しかし、カイクラの通話録音機能で通話の優先度を判断し、迅速なコミュニケーションを実現しています。顧客の声のニュアンスから、重要な電話を判断できるからです。
以前は顧客からの電話で言った言わない問題に直面することもありましたが、自動の通話録音を取り入れたことでトラブル防止に役立っているそうです。
通話録音は解約などの顧客の意思確認の手段にもなっています。同社では従来、顧客が契約を解約する際に解約通知書を郵送しなければなりませんでした。
しかし、通話録音を取り入れてからは顧客が電話口で解約を伝えるだけで代用できるようになり、手続きの効率化も実現しました。
参考:株式会社駐車場をさがせ様
通話録音で業務効率化とトラブル回避に役立てている企業は多くあります。カイクラの機能および他の導入事例が知りたい方は、以下よりご覧ください。
\電話対応の負担が減ったとの声多数!/
カイクラの通話録音機能をチェック
▲無料ダウンロード資料あり
まとめ:ツール活用でカスハラ事案を回避しよう!

さまざまな顧客対応をする中で、トラブルに発展することはよくあります。
カスハラ行為をする顧客への対処は、規定にあわせて実施することが重要です。くれぐれも現場の従業員に委ね、過度な負担を与えないようにしましょう。
また、電話での顧客対応においてはトラブルを記録する方法の1つとして、自動で通話録音ができるツールの活用が役立ちます。詳しくは以下よりコミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」をご確認ください。
\利用社数3,000社以上!/
カイクラの詳細を見る
▲無料ダウンロード資料あり













