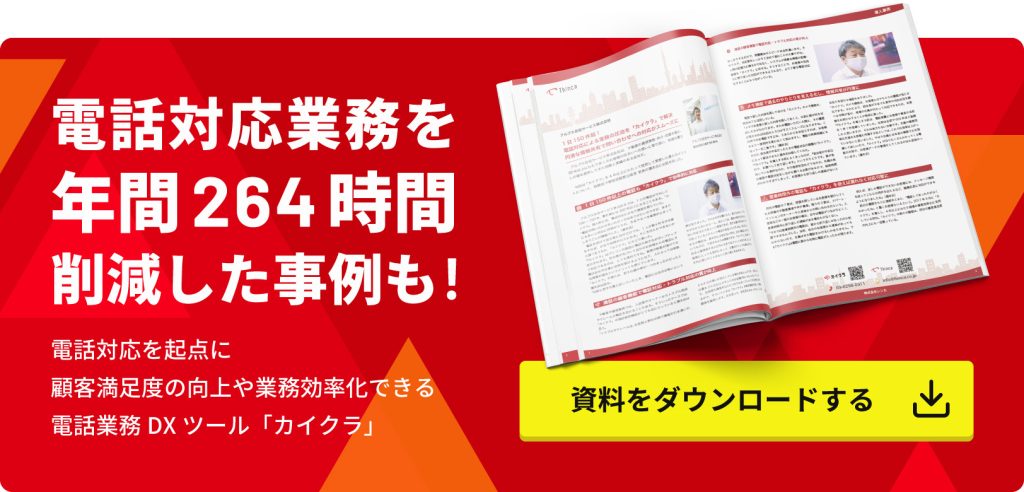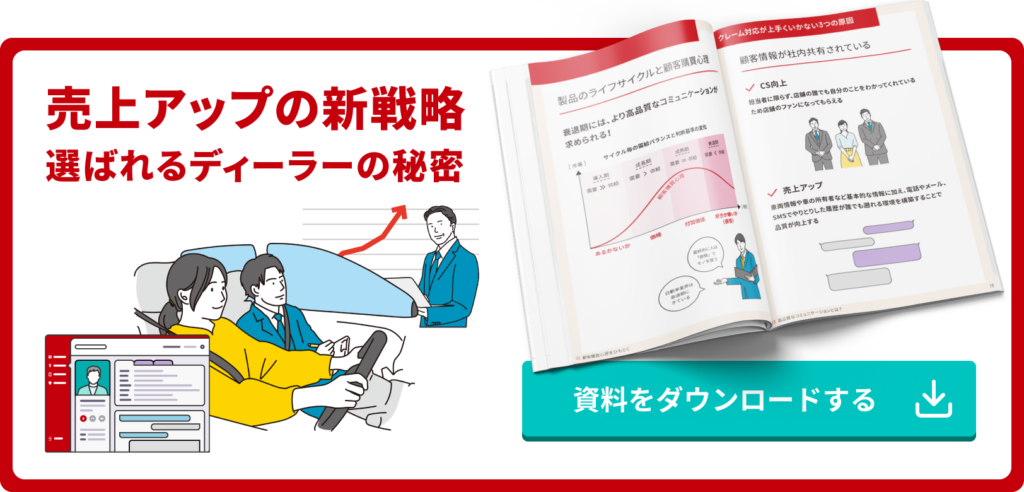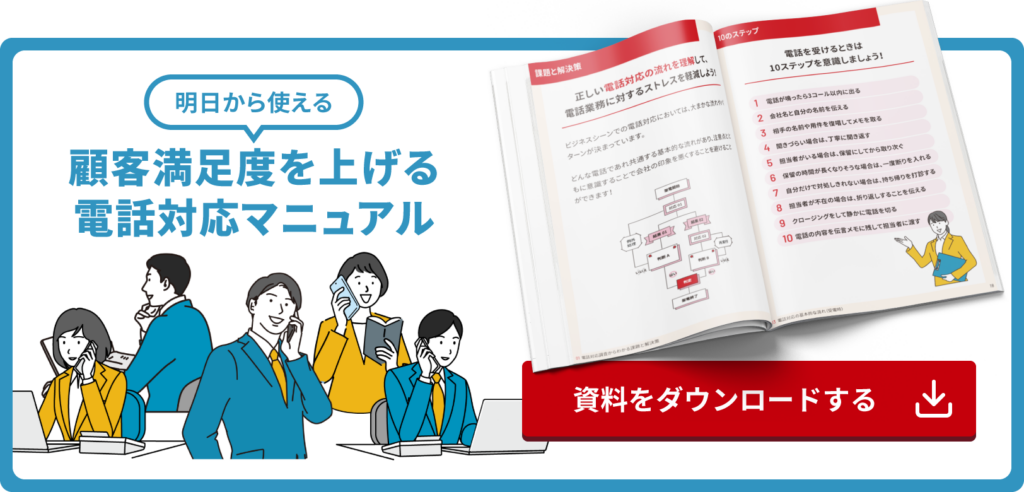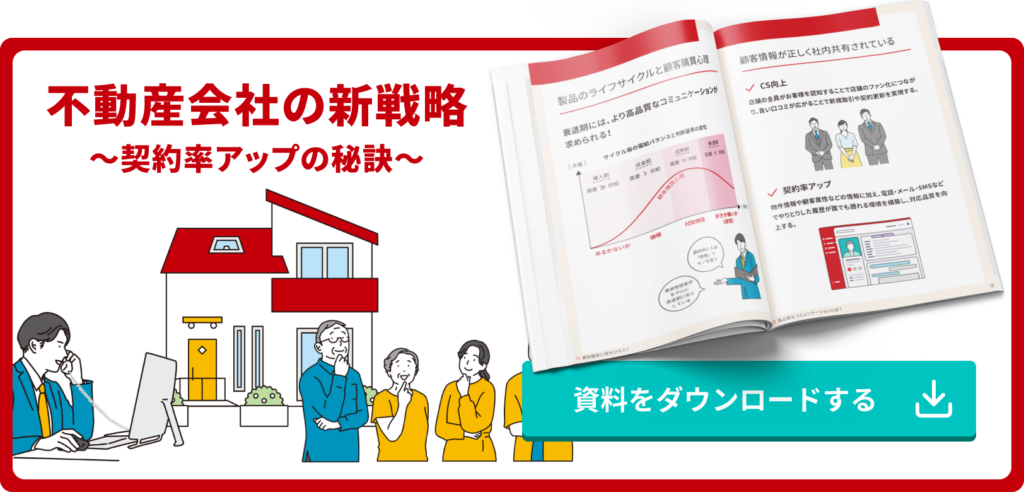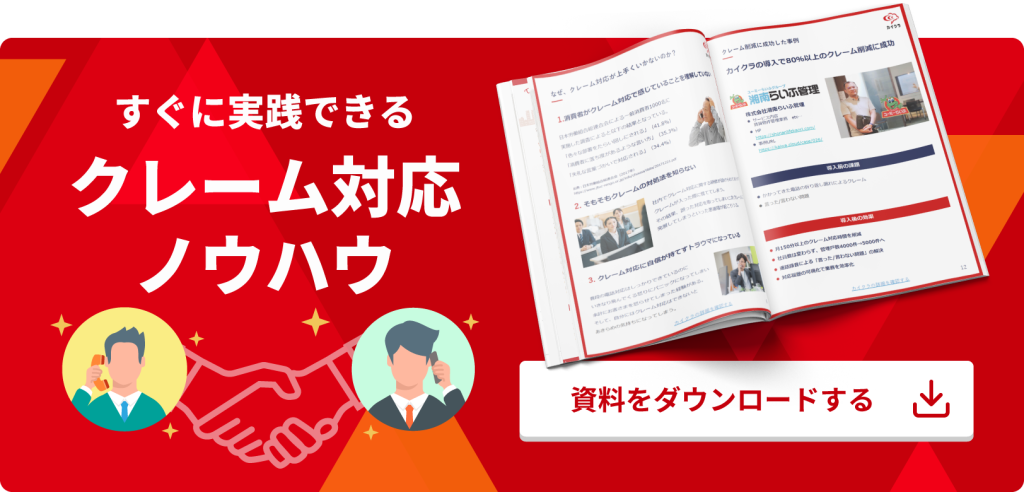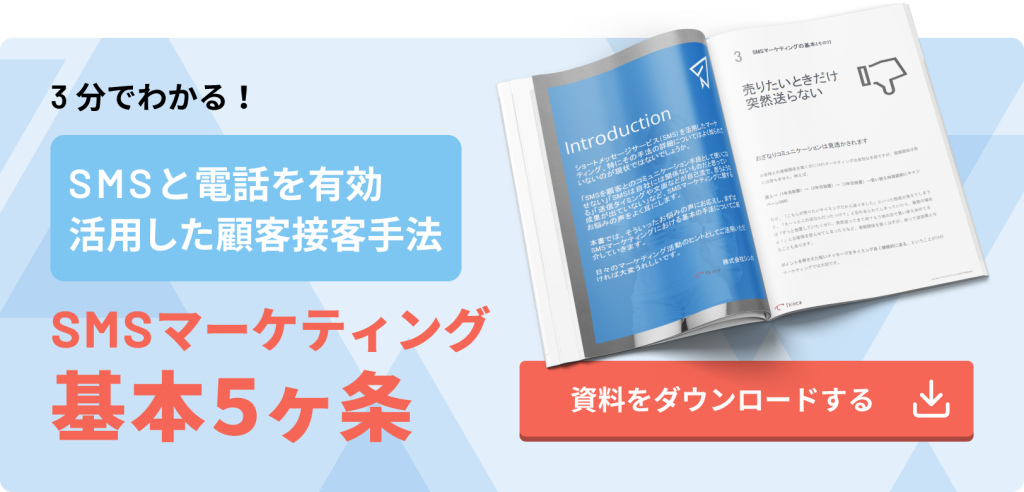「中小企業もDXに取り組むべきだろうか」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、中小企業こそDXに取り組むべきです。なぜならDXによって業務の効率化や自動化、生産性アップなどが期待できるから。さらには顧客満足度や売上アップにもつながります。
とはいえ、なぜ中小企業にDXが必要なのかは、なかなかわかりにくいですよね。
そこで今回は、
- DXを推進した企業の成功事例
- DXの未導入によって、多くの企業が「2025年の崖」に直面する
- 中小企業へのDX導入がもたらすメリット
- 中小企業のDX導入を成功させるポイント
を紹介します。
最初に、DX推進に成功した企業の例を6つ見てみましょう。
なお「DX推進の一環として、電話業務の効率化を行いたい」とお考えの方は、顧客接点クラウド「カイクラ」の導入を検討してみませんか。電話の自動録音や通話のテキスト化など、便利な機能が揃っています。
電話業務の効率化を検討している方は、ぜひ以下からカイクラをチェックしてください。
\業務効率化と顧客満足度アップを実現!/
カイクラがよくわかる資料はこちら
▲たった4つの回答で無料ダウンロード可能
DXを推進した企業の成功事例

続いては、中小企業がDXに取り組んだときをイメージしやすくするために、以下6つの成功事例を紹介します。
- 日進工業株式会社
- のぼり屋工房株式会社
- 碌々産業株式会社
- 株式会社ベネッセホールディングス
- SGホールディングス株式会社
- トヨタカローラ香川株式会社
事例1:日進工業株式会社
日進工業株式会社はDX化によって、稼働率アップに成功しています。
もともと日進工業株式会社は、日本のものづくりを存続させるために、DX化を検討していました。そこで製造ラインの稼働状況を見える化するために、MCM Systemを開発します。
モニターで稼働率や停止状況を把握できるようになり、生産性の低いラインの洗い出しに成功。稼働率を50%から90%まで引き上げました。
稼働率を正確に把握することで、受注できる数も的確に判断できるようになっています。
中小規模製造業の製造分野におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)のための事例調査報告書
https://www.ipa.go.jp/files/000084035.pdf
事例2:のぼり屋工房株式会社
のぼり屋工房株式会社は岡山県にある企業で、のぼり旗やのれんなど販促物を製造しています。DXによって、業務の自動化と効率化に成功しています。
DXに取り組むきっかけは、従業員の異動。1日5時間ほど受発注の管理を担当していた社員の異動が決まったものの、後任が見つかりません。
またICT分野による業務の自動化を考えていたこともあり、RPA製品である「WinActor」を導入しました。
RPAとは、人工知能などを活用してルーティーンワークを自動化できるもの。業務の効率化や生産性アップのために活用されることが多いです。
のぼり屋工房株式会社もWinActorによって、見積もりシステムのデータを自動で抽出。エラーは社員が確認しますが、それでも作業時間を1日2時間まで短縮しています。
出典:NTT DaTa「WinActor®導入事例【中小企業事例/のぼり屋工房株式会社】見積システムから基幹システムへのデータ引き継ぎをRPAに移植、従業員異動にともなう人手不足問題を解決」
https://winactor.com/case/winactoruse/5961/
事例3:碌々産業株式会社
碌々産業株式会社は、東京都にある加工機製造を行っている会社です。DXによって、製品の動作不良が発生する原因究明および不具合が発生しない使い方のサポートができるようになりました。
製品が高頻度で故障する。しかし販売先の約7割が台湾で、かつお客様がどのように使用しているのか把握しにくい。このような課題を抱えていました。
そこで碌々産業株式会社では、販売する加工機のあらゆる部分にセンサーを設置し、オンラインでデータを収集できるようにしました。センサーを通じて、どのように製品が使用されているのか、遠隔監視が可能です。
その結果、不具合の原因究明や正しい使い方のサポートを行えるようになりました。
出典:中小規模製造業がDXを推進するための動画のご紹介(事例1:納入機器をIoTで遠隔監視!碌々産業様)
https://local-iot-lab.ipa.go.jp/article/office-iot-2011111424.html
事例4:株式会社ベネッセホールディングス
中小企業のDX推進事例として挙げられるのが、株式会社ベネッセホールディングスです。同社は、岡山県に本社のある会社です。国内教育事業では、以下のようにデジタルテクノロジーを活用してサービスを提供しています。
- (小中学生向け)個人別の学習コンテンツを提供する「学習専用タブレット」
- (高校向け)教育プラットフォーム「Classi」
- (社会人向け)オンライン学習サービス「Udemy」
2021年5月1日、株式会社ベネッセホールディングスは、経済産業省が定める「DX認定事業者」を取得しています。
出典:ベネッセホールディングス、経済産業省が定める「DX認定事業者」に選定
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000910.000000120.html
事例5:SGホールディングス株式会社
佐川急便でおなじみのSGホールディングス株式会社は、経済産業省が選定する「DX銘柄2022」の1つです。
DX導入により「AIによる配送ルート最適化」「AI-OCRによる伝票デジタル化」を実現しています。現在は「不在再配達削減」や「顧客・同業他社との連携を深める物流プラットフォームサービス」の構築に取り組んでいます。
出典:「DX銘柄2022」選定企業レポート
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/keiei_meigara/dx_meigara.html
事例6:トヨタカローラ香川株式会社
トヨタカローラ香川株式会社は電話対応にDXを取り入れることで、業務の効率化と生産性アップに成功しています。
トヨタカローラ香川株式会社は、店舗あてに5分に1回の電話を受けていました。また担当者が不在の場合、「誰がいつ電話をかけてきたのか」などの情報を他スタッフから受け継がなければなりません。
共有がスムーズに進まずお客さまに再確認する、不在のお客さまへのかけ直してもつながらないなどの課題を抱えていました。
そこで「カイクラ」を導入したところ、電話対応による時間のロスを大幅に削減しています。
具体的に役立った機能は、以下の2つ。
- 着信時に顧客情報を表示するポップアップ
- 伝言メモによる情報共有
ポップアップで顧客情報がわかることで、担当者に直接つなぐことが可能です。また伝言メモによって内容をしっかりと確認でき、お客さまをお待たせすることも少なくなりました。
出典:カイクラ「タイムロスが続いていた電話対応「カイクラ」導入後、すぐに時短効果が担当者以外でも商談予定を組めるように」
https://kaiwa.cloud/case/022/
\業務効率化と顧客満足度アップを実現!/
カイクラがよくわかる資料はこちら
▲たった4つの回答で無料ダウンロード可能
このようにDXに成功している中小企業も多いですが、導入にあたって準備も必要です。次で詳しくお伝えしますね。
DXの未導入によって、多くの企業が「2025年の崖」に直面する

DXの未導入によるリスクについて、以下の観点から紹介します。
- 経済産業省が提唱する「2025年の崖」
- 中小企業におけるDXの現状
データは以下を参考にしているため、気になる方はあわせてご確認ください。
出典:経済産業省「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/pdf/20180907_01.pdf
経済産業省が提唱する「2025年の崖」とは
経済産業省はDXに取り組まなかった場合、以下のリスクを想定しています。
- 既存システムの過剰なカスタマイズによってデータを活用できない
- IT人材が約43万人不足、かつ古いシステムを理解できる人材も少ない
- 古いシステムの維持・管理費が高額で、IT予算の9割を占めてしまう
上記の課題が発生した結果、2025年以降に最大12兆円の経済損失が発生すると予測。これを「2025年の崖」と呼んでいます。
2025年の崖による経済損失を防ぐために、経済産業省などが中心となってDXを推進しています。
中小企業におけるDXの現状:推進しているのは36.5%
積極的にDX化に取り組んでいる中小企業は、まだまだ少ないのが現状です。
実際に日経BPの調査によると、DXを積極的に推進しているのは36.5%でした。
企業の規模別に見ると、以下の通り。
【企業規模別に見るDXの推進状況】
- 300人未満:21.8%
- 300〜1,000人未満:34.4%
- 1,000人以上:57.2%
- 5,000人以上:80.3%
また取り組みへの意欲と成果について、以下の結果が明らかになっています。
【DXへの意欲と成果】
- 本気で取り組み、目覚ましい成果をあげている:25.1%
- 本気で取り組み、一定の成果をあげている:25.1%
- 本気で取り組んでいるが、まだ成果をあげていない:39.4%
- PoC(概念検証)という位置づけである:33.9%
取り組んでいるものの、「成果をあげるのが難しい」と感じている企業が多いです。
出典:日経BP「日経BP総研、国内900社の「デジタル化実態調査」を発表デジタルトランスフォーメーションの推進企業は36.5%、企業規模で大きな差」
https://www.nikkeibp.co.jp/atcl/newsrelease/corp/20191125/
中小企業のDXに対する取り組みや実態について、詳しくは「中小企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)における実態と課題とは?解決策もあわせて紹介」をご一読ください。
[clink url=”https://kaiwa.cloud/media/dx/chusho-dx/”]
ここまで中小企業とDXの関係を解説しました。
まだまだ取り組んでいる企業は少ないですが、DXは中小企業こそ必要です。その理由を次で詳しくお伝えしますね。
DX導入が中小企業にもたらす4つのメリット

ここからは、中小企業にDXが必要な理由として、以下の4つが挙げられます。
- 業務プロセスの自動化によって効率化を実現できる
- 災害などイレギュラーでも事業を継続しやすい
- 未来のリスクを予測し、トラブルを防止できる
- 優秀な人材を採用したり離職を防いだりしやすい
どういうことか、詳しく紹介します。
メリット1:一部の業務プロセスを自動化でき、効率化につながる
1つ目は「一部の業務プロセスを自動化でき、効率化につながる」です。
DXはたとえば、以下の身近な業務に適用できます。
- 売上入力を手書きから自動計算システムに変更
- 顧客管理システムを導入し、自動でメールマガジンを配信
一部の業務を自動化することで時間に余裕ができ、コア業務に多くの時間をかけることが可能です。
メリット2:災害時などイレギュラーが起きても事業を存続できる
2つ目は「災害時などイレギュラーが起きても事業を存続できる」です。
2020年は新型コロナの影響でテレワークを導入するなど、事業の取り組み方が変化した企業は多いのではないでしょうか。また地震など災害によって、事業の存続が難しくなる可能性もあります。
DXに取り組んでいると、イレギュラーが発生しても事業を継続しやすくなります。
たとえば、クラウド上でデータを保管できる顧客管理システム。IDとパスワードがあればブラウザからアクセスできるため、自宅からでも顧客情報を閲覧できます。
テレワークの導入などもスムーズになり、イレギュラーが起きても通常通りの対応が可能です。
メリット3:未来のリスクを予測し、トラブルを防止できる
3つ目は「未来のリスクを予測し、トラブルを防止できる」です。
製造業などは機械を使用することが多いですが、故障のタイミングなどはなかなか予測できません。急な故障で納期に遅れることは、避けたいです。
実はDXによって、故障時期を予測できます。
たとえばIoTでは、機械のデータを集めてAI分析をかけることで、小さな機械の変化を察知。予測をもとに早めに修理に出すことで、作業が止まることはありません。
リソースが限られている中小企業だからこそ、DXを活用してトラブルを防ぐことが重要です。
メリット4:優秀な人材を採用したり離職を防いだりしやすい
4つ目は「優秀な人材を採用したり離職を防いだりしやすい」です。
DXを活用して業務効率化やリスクへの対処を行うと、業務の効率化につながります。業務が効率化されると生産性アップや労働時間の短縮効果が期待でき、働きやすさの改善にもつながるでしょう。
DX推進によって働きやすくなった結果、求職者から見て魅力的な企業となり、採用力の向上につながります。また、働きやすい環境になった結果、従業員の離職率を低下させる効果も期待できます。
ここまで、中小企業がDX導入によって受けられるメリットを紹介しました。
- 業務プロセスの自動化によって効率化を実現できる
- 災害などイレギュラーでも事業を継続しやすい
- 未来のリスクを予測し、トラブルを防止できる
- 優秀な人材を採用したり離職を防いだりしやすい
DX導入を進めることで、上記のメリットを受けられる可能性があります。注意点を挙げると、DX推進のためツールを導入しすぎると、従業員が使いこなせなかったり管理が大変になったりします。
ツール導入の際は、直感的にわかりやすく操作できるか、他のツールと連携しやすいかを意識しましょう。
ちなみに顧客接点クラウド「カイクラ」では、顧客情報や対応履歴を一元管理できます。他ツールとの連携も可能で、かつ直感的でわかりやすい画面レイアウトになっています。
顧客管理や電話業務のDX化を検討している方は、ぜひチェックしてください。
\業務効率化と顧客満足度アップを実現!/
カイクラがよくわかる資料はこちら
▲たった4つの回答で無料ダウンロード可能
中小企業でDX導入を成功させるために必要な4つのポイント

続いては、中小企業のDXにおいて必要な準備として、
- 目的の確認
- 予算の確保
- 対象ツールの確認
- 補助金の活用
の4つを解説します。
ポイント1:DXに取り組む目的をハッキリさせる
まずはDXに取り組む目的を、社内でハッキリさせましょう。
経営陣がDX化を積極的に検討しても、活用するのは現場の社員です。DXを推進する目的やビジョンを共有しておかないと、ただ指示に従うだけで終わりかねません。
DX化によってどういう未来が得られるのか、しっかりと共有しておきましょう。
ポイント2:予算を確保する
DXに取り組むときは、予算をある程度確保しておくことが必要です。導入には数万〜数百万円かかるツールもあり、余裕のある計画が欠かせません。
予算の確保が難しい場合は、補助金を活用しましょう。種類にもよりますが、ツール導入費用の一部を負担してもらうことが可能です。
ポイント3:身近な業務で活用できそうなツールを探す
DXの導入は、まず身近な業務の改善から取り組むのがおすすめです。
その理由は「身近な業務の改善の方が取りかかりやすいうえに、業務の効率化など成果が見えやすいため」。
導入の成果を実感しやすいことから、電話対応など毎日の業務から見直すことをおすすめします。
またDXツールの中にも、中小企業向けに低予算で利用できるツールは数多くあります。
気になる方は、「【低予算でDX】中小企業におすすめのデジタルトランスフォーメーション(DX)サービスと成功事例」をご一読ください。
[clink url=”https://kaiwa.cloud/media/dx/dx_teiyosan/”]
ポイント4:補助金を活用する
業務のDX化を検討している企業は、補助金を活用できる可能性があります。
たとえば2022年6月現在、以下の補助金があります。
- ものづくり補助金
- IT導入補助金2022
この他にも、中小企業のIT化をサポートする補助金があります。ただし時期によって実施されている補助金に違いもあるため、事前に官公庁のページをチェックがおすすめです。
また、補助金は申請することでかならず貰えるわけではありません。条件を満たさない申請や書類の不備などがある場合は、申請が通らない可能性もあります。
補助金を当てにした業務のDX推進は、あまりおすすめできません。
中小企業がDXに取り組むことで業務の効率化が実現しやすくなる

今回は、中小企業のDXへの取り組みを解説しました。
日本の中小企業でDXに取り組んでいる企業は少ないのが現状です。しかし、経済産業省が提唱する「2025年の崖」のように、DXに取り組まないリスクも大きいです。
中小企業がDXに取り組むべき理由として、以下の4つを紹介しました。
- 業務プロセスの自動化によって効率化を実現できる
- 災害などイレギュラーでも事業を継続しやすい
- 未来のリスクを予測し、トラブルを防止できる
- 優秀な人材を採用したり離職を防いだりしやすい
導入前に必要な準備は、以下の4つです。
- 目的の確認
- 予算の確保
- 対象ツールの確認
- 補助金の活用
本記事を参考に、身近な業務からDXへの移行を検討してみてはいかがでしょうか。
なお、電話対応の業務効率化や顧客対応の改善をしたい場合は、多数の機能を揃えたシステムの導入がおすすめです。
たとえばカイクラには、過去の通話内容を把握しやすい「通話録音機能」や、販促や顧客とのコミュニケーションにも活かせる「SMS機能」などあります。誰でも簡単に使えるうえ直感的に操作しやすいUIのため、ツールの導入に不安を感じている人にも安心です。
カイクラがよくわかる資料は、以下からダウンロードのうえご確認ください!
なお、電話応対の業務効率化や顧客対応の改善をしたい場合は、多数の機能を揃えたシステムの導入がおすすめです。
たとえばカイクラには、過去の通話内容を把握しやすい「通話録音機能」や、販促や顧客とのコミュニケーションにも活かせる「SMS機能」などあります。誰でも簡単に使えるうえ直感的に操作しやすいUIのため、ツールの導入に不安を感じている人にも安心です。
カイクラがよくわかる資料については、以下からダウンロードのうえご確認ください!
\業務の効率化・負担が減ったとの声多数!/
カイクラがよくわかる資料はこちら
▲無料ダウンロード資料あり