ビジネスにおけるカスハラ(カスタマーハラスメント)は、従業員の心身に深刻な影響を与える社会問題です。そして、カスハラが原因で精神障害を発症した場合、労災保険の対象となる可能性があります。
2023年9月1日には、厚生労働省の定める労災認定基準が改正され、カスハラを含む「顧客・取引先・施設利用者等からの著しい迷惑行為」が労災認定の評価対象として明確化されました。
本記事では、「カスハラで労災は認定されるのか?」などの疑問に答えながら、最新の認定基準、具体的な申請手順、過去の事例、そして企業が取るべき具体的な対応策をわかりやすく解説します。

カスタマーサクセス領域における業務改善のプロフェッショナル。株式会社シンカのマネージャーとして、3000社以上の「カイクラ」導入企業を支援するチームを統括。担当業務の多様化・複雑化に伴う「タスクの抜け漏れ」や「業務の属人化」といった、多くの企業が抱える課題に対し、ITツールを活用した業務プロセスの抜本的な再構築を主導。現場の課題解決から事業成長までを幅広く支援する、電話コミュニケーションDXのプロ。
カイクラでは、カスハラ対策の基本をまとめたお役立ち資料も無料で配布していますので、ぜひご活用ください。
\社労士が監修!/
カスハラ対策の資料をダウンロード
▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説
カスハラは労災認定される!定義や評価対象は?

カスハラは、顧客からの理不尽な要求や言動のことです。近年、社会問題として広く認知されるようになり、カスハラが原因で精神疾患を発症した場合、労災保険の対象となる可能性があります。
ここでは、まずカスハラの定義や具体例、そしてカスハラが労災認定される際の重要な考え方を解説します。
- カスハラの定義と具体例
- カスハラによる労災の業務起因性とは?
- カスハラとパワハラとの違い
それぞれ詳しくみていきましょう。
カスハラの定義と具体例
カスハラは、顧客や取引先、施設利用者などが、業務の適正な範囲を超えて従業員に暴言や脅迫、不当な要求などをおこなうことを指します。
具体的には、以下の行為がカスハラに該当します。
- 長時間にわたり拘束する
- 人格を否定するような罵詈雑言を浴びせる
- 過度な謝罪や金銭を要求する
- 暴力をほのめかすなどの脅迫行為をする
- SNSなどを利用して嫌がらせをおこなう
より詳しいカスハラの事例は、以下の記事で紹介しています。

カスハラによる労災の業務起因性とは?
カスハラが原因で精神障害を発症した場合、労災認定のためには「業務起因性」であることが必要です。業務起因性とは、その傷病が業務と因果関係があることを指します。
カスハラの場合、業務起因性を判断するうえでは、以下の点が考慮されます。
- カスハラが勤務中や業務に関連して発生したか
- 会社の指示や対応の範囲内で起きたことか
- 私的なトラブルではないか
労災としてカスハラを立証するには、被害に遭った日時や内容、対応した状況などを時系列でまとめた記録や、第三者の証言、通話録音、防犯カメラの映像などの客観的な証拠が必要です。
カスハラとパワハラとの違い
カスハラとパワハラは、どちらもハラスメントの一種ですが、最も大きな違いは「加害者」が誰なのかです。
- カスハラ:顧客や取引先など、社外の人間が加害者
- パワハラ:上司や同僚など、社内の人間が加害者
ただし、カスハラを受けた従業員が、その後の会社の対応によってさらに精神的負担を強いられた場合、カスハラとパワハラが同時に発生していると判断される可能性もあります。
このようなケースでは、会社の管理体制が適切だったかどうかも、労災認定の重要な論点です。
カスハラが追加された労災認定基準改正【2023年】のポイント

2023年9月1日、厚生労働省は「精神障害の労災認定基準」を改正しました。今回の改正では、カスハラが労災認定の評価対象として明確化され、より実態に即した判断が可能になりました。
主な改正ポイントは以下の5つです。
- 「顧客等からの著しい迷惑行為」の追加
- 「感染症等の危険性が高い業務」の追加と評価の考え方
- 心理的負荷評価(強・中・弱)の具体例拡充
- 特別な出来事がなくても悪化部分の業務起因性を認める見直し
- 医学意見収集の効率化
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.「顧客等からの著しい迷惑行為」の追加
今回の改正で、カスハラが「顧客等からの著しい迷惑行為」として労災認定の具体的な出来事として新たに追加されました。
この追加がおこなわれたのは、「業務による心理的負荷評価表」においてです。業務による心理的負荷評価表は、仕事が原因でどれだけ強いストレスを受けたのか、心理的負荷の強さを「強・中・弱」で判断する評価基準です。
この評価表に「こんな出来事があれば『強』と判断する」という具体例がリストアップされています。
今回、このリストにカスハラの事例がはっきりと書き加えられました。
具体的には、「顧客等から、人格や人間性を否定するような言動など、業務の範囲を逸脱した著しい迷惑行為を受けた」場合が対象となります。
たとえば、以下のようなケースが想定されます。
- 土下座を強要される
- SNSで個人を特定され、誹謗中傷を受ける
- 何時間にもわたって電話で罵倒され続ける
このような行為があった場合、その悪質さや継続性などを総合的に評価し、労災認定の判断がおこなわれます。
具体例が明記されたことで、これまでよりも労災認定されるかどうかの判断がわかりやすくなりました。
また、パワハラとカスハラが同時に発生した場合には、より強いストレスがかかったと評価される可能性があります。
2.「感染症等の危険性が高い業務」の追加と評価の考え方
新型コロナウイルス感染症のパンデミックを背景に、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」出来事も追加されました。医療従事者や介護職員など、常に感染リスクにさらされている業務が主な対象です。
一見、カスハラとは無関係に見えるかもしれません。しかし、この項目が重要なのは、感染対策がきっかけで、カスハラが発生するケースがあるからです。
たとえば、以下のような「二重のストレス」にさらされる状況が予想されます。
- マスク着用をお願いしたところ、患者「命令するのか!」と罵声を浴びせられた
- 施設の面会を制限した結果、利用者の家族から「お前らのせいで会えない」と執拗なクレームを受けた
このように、「感染リスクへの恐怖」と「顧客からの心無い言動」が重なることで、より強い心理的負荷がかかったと評価され、労災認定につながる可能性が出てきます。
3.心理的負荷評価(強・中・弱)の具体例拡充
労災認定の判断に使われる「心理的負荷評価表」では、個別の出来事を「強」「中」「弱」の3段階で評価します。今回の改正では、カスハラや感染症リスクなど、新たな出来事が追加されたことに加え、既存の出来事についても具体例が拡充されました。
とくに、カスハラにおいて、心理的負荷が「強」と評価される代表的なパターンは、大きく分けて2つあります。
1つ目は、「たった一度でも、極めて悪質なケース」です。一度の体験で心に深い傷を負い、精神疾患を発症する可能性が高いような出来事が該当します。労災認定基準では「特別な出来事」と呼ばれます。
▼具体例
- 顧客から暴行を受けたり、「殺すぞ」と脅迫されたりした
- 土下座での謝罪を強要され、その様子を撮影された
- 性的被害を受けた
2つ目は、「繰り返し、執拗に続くケース」です。一つひとつの出来事は「中」程度でも、同じような嫌がらせが執拗に繰り返されることで、心身が追い詰められていく状況です。
▼具体例
- 毎日のように数時間にわたるクレーム電話があり、罵倒され続けた
- SNS上で、数か月にわたり執拗な誹謗中傷を受けた
今回の改正で、こうしたカスハラの具体例が評価表に明記されたことで、被害を受けた労働者が「自分のケースは労災の対象になるかもしれない」と判断しやすくなりました。
4.特別な出来事がなくても悪化部分の業務起因性を認める見直し
これまでは、精神疾患の既往症がある場合、業務が原因で病状が悪化したとしても、労災認定が困難なケースがありました。
しかし今回の改正で、業務による強い心理的負荷が原因で精神疾患が悪化した場合、たとえ直近6か月以内に「特別な出来事」がなかったとしても、悪化した部分は業務起因性があるとして労災認定される可能性が高まりました。
これは、反復・継続するカスハラなどによって、心理的負荷が徐々に蓄積していくケースに対応したものです。
5.医学意見収集の効率化
労災認定の審査プロセスにおいて、専門医の意見収集も効率化されています。今までは、複数の専門医の意見を聞くことが一般的でしたが、今回の改正で、とくに判断が難しいケースを除き、専門医1名の意見で決定できる仕組みになりました。
これにより、労災認定までの審査期間の短縮が期待でき、申請者や企業が準備すべき医療情報もより明確になりました。
2023年の改正によって、カスハラによる精神障害の労災認定は、より客観的かつスムーズにおこなわれるようになります。それでは次に、具体的な認定要件と評価プロセスを詳しくみていきましょう。
カスハラ労災の認定要件と評価プロセス
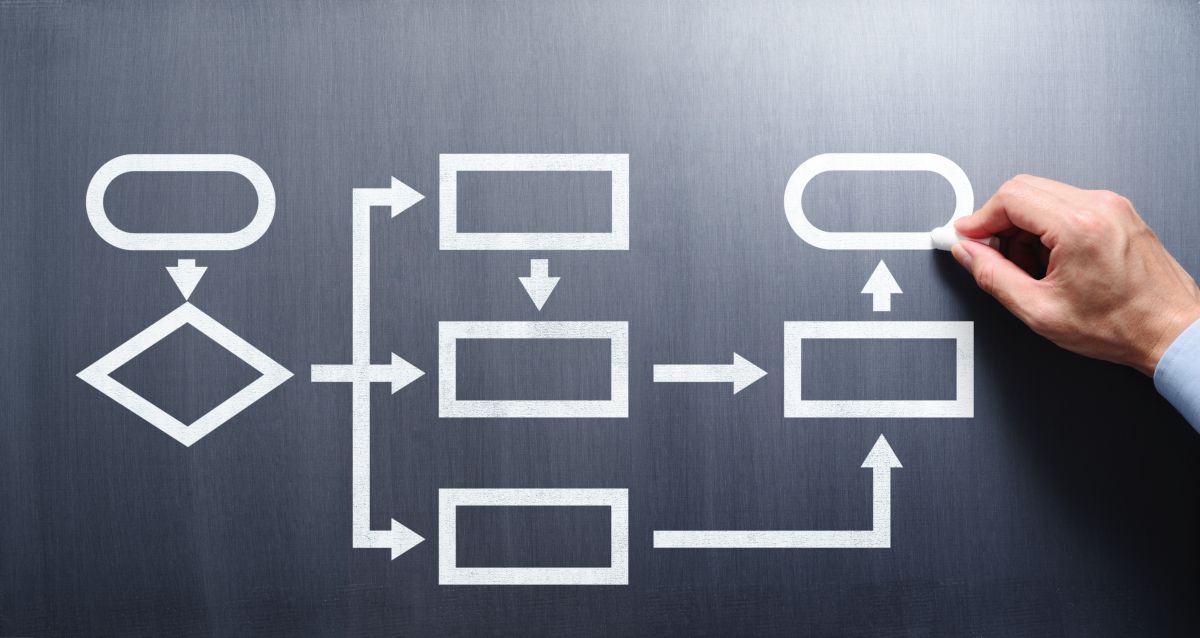
カスハラによる精神障害で労災認定を受けるためには、定められた要件を満たすことが必要です。労災認定は、単に「カスハラを受けた」事実だけで判断されるのではなく、複数の要素を総合的に考慮して決定されます。
ここでは、以下の3つに分けて解説します。
- 3つの認定要件
- 心理的負荷評価表の使い方
- 認定のフローチャートと判断の着眼点
詳しくみていきましょう。
1.3つの認定要件
精神障害で労災認定を受けるには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1つ目の要件は、業務による強い心理的負荷がある出来事があることです。
労働者が発病前おおむね6か月以内に、業務に関連して精神的なストレスとなる出来事があったかどうかを判断します。出来事の有無を証明するために、カスハラを受けた日時、内容、対応状況などがわかる記録が必要です。
2つ目の要件は、精神障害を発病していることです。
精神科医や心療内科医などの専門医から、精神疾患の診断を受けているかどうかがこの要件に該当します。診断書やカルテなどが、この要件を満たすための重要な資料となります。
3つ目の要件は、業務起因性が認められることです。
発病した精神障害が、業務による心理的負荷と因果関係があることを証明する必要があります。精神疾患の既往症や、業務外でのトラブルなど、業務と関係ないストレスがないかどうかも考慮されるためです。
これら3つの要件はそれぞれ独立しているものではなく、相互に関連しています。たとえば、「業務による出来事」の心理的負荷が「強」と評価されれば、「業務起因性」が認められやすくなります。
2.心理的負荷評価表の使い方
労災認定の判断において、中心的な役割を果たすのが「心理的負荷評価表」です。この評価表は、業務上の出来事によってどのくらいの心理的負荷があったのかを客観的に判断するために使われます。
評価は、下記の流れで進められます。
- 出来事の選択:最初に、労働者が経験した業務上の出来事を、評価表の出来事の類型に照らし合わせる
- 強度判定:出来事の頻度、継続期間、悪質性などを考慮して、心理的負荷の強度を「強」「中」「弱」の3段階で評価する
- 総合評価:出来事そのものの強度に加え、その後の対応(会社の支援体制や、労働者自身の対応など)も考慮して、総合的に評価する
とくに、カスハラの場合は、以下の要素が心理的負荷の強度を上げる要因になる可能性があります。
- 同時に複数のカスハラ行為が起きた
- 第三者が被害に巻き込まれた
- 身体的な症状(頭痛や吐き気など)を発症した
これらの要素を客観的な証拠とともに提示することが重要です。
3.認定のフローチャートと判断の着眼点
労災認定の申請から決定までは、一般的に以下の流れで進められます。
- 申請受付: 労働基準監督署に申請書を提出
- 調査: 労働基準監督官が、労働者や会社への聞き取り、資料確認などで事実を調査
- 医学意見の聴取: 必要に応じて、専門医の意見を聴取
- 決定: 調査結果と専門医の意見をもとに、認定・不認定を決定
このフローの途中で、とくに問題になりやすいのは「事実認定」と「医学的な証拠不足」です。
事実認定では、 申請内容と会社の主張に食い違いがある場合、事実関係の確認に時間がかかります。また、精神疾患の診断が曖昧だったり、カスハラと発病の因果関係が不明確だったりするなど、医学的な証拠が不足している場合も審査がスムーズに進まない可能性があります。
発病の時期は、自殺事案の場合でも、発病時期を推定して判断される場合があります。
カスハラを労災申請する手順と必要書類
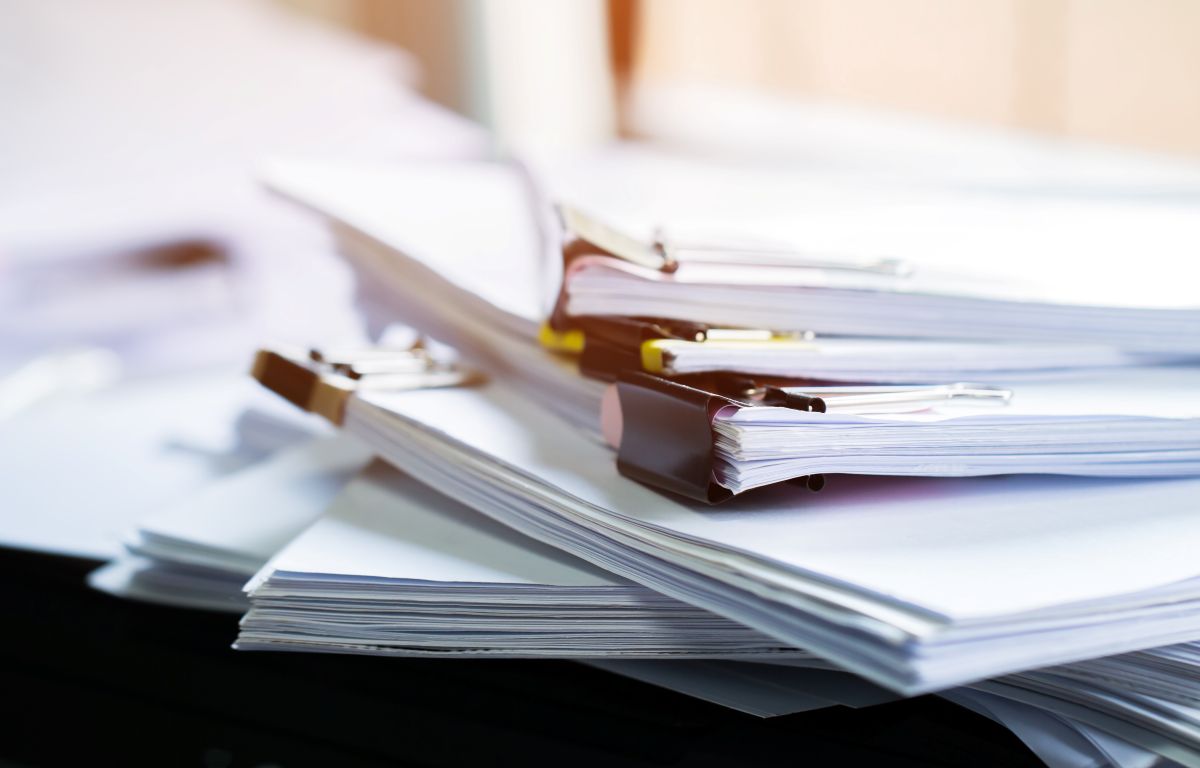
カスハラによる精神障害で労災認定を受けるためには、適切な手順で申請を進める必要があります。準備不足で申請してしまうと、審査が長引いたり、不認定になったりする可能性があるためです。
ここでは、労災申請をおこなう際の具体的な手順と、その際に必要となる書類を解説します。
- 申請前の準備
- 申請の流れ
- 審査期間の目安と不服申立て
準備不足にならないよう、必要なことをチェックしていきましょう。
1.申請前の準備
労災申請をスムーズに進めるためには、申請前の準備が重要です。ここで意識したいポイントは2つあります。
1つ目は、カスハラの事実を客観的に証明できる一次記録の収集です。具体的には、以下が一次記録として認められます。
- 通話の録音や通話記録
- メールやチャットのログ
- 防犯カメラの映像や音声
- カスハラを受けた状況を詳細に記録したメモ
2つ目は、早期に医療機関を受診し診断書を確保することです。
カスハラによる心身の不調を感じたら、できるだけ早く精神科や心療内科を受診しましょう。その際に、カスハラが原因であることを医師に伝え、診断書を作成してもらいます。診断書は、精神障害の存在を証明する重要な証拠です。
2.申請の流れ
労災申請は、原則として労働者本人が、労働基準監督署長に対しておこないます。
会社の協力が得られない場合でも、労働者本人が直接、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に必要書類を提出することで申請は可能です。
労災申請の際に会社からの事業主証明が必要になるケースもありますが、会社の協力が得られない場合でも、申請できます。まずは最寄りの労働基準監督署や労働局に相談してみましょう。
3.審査期間の目安と不服申立て
労災申請の審査期間は、ケースによって異なります。一般的には数か月かかることが多く、複雑なケースでは1年以上かかることもあります。
もし審査の結果に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求がおこないましょう。
労災となるカスハラで企業が負う責任と実務対応

カスハラは従業員個人の問題ではなく、企業全体で取り組むべき課題です。カスハラによる精神疾患が労災と認定されると、企業は以下の責任を負う可能性があります。
- 安全配慮義務と賠償リスク
- 相談窓口の設置と初動対応
- 教育・研修・対応マニュアル化と記録の徹底
ここでは、企業が取るべき実務的な対応策を解説します。
1.安全配慮義務と賠償リスク
企業には、従業員が安全で健康に働けるよう、必要な配慮をおこなう「安全配慮義務」があります。この義務を怠り、カスハラによって従業員が精神疾患を発症した場合、労災認定の有無に関わらず、企業は民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。
労災保険給付は、すべての損害(慰謝料など)をカバーするわけではありません。そのため、別途、民事訴訟で賠償を求められるリスクがあります。裁判では、再発防止体制の不備などが不利な判断材料となるため、日頃からの対策が重要です。
2.相談窓口の設置と初動対応
カスハラが発生した際に、従業員が安心して相談できる窓口を設置することは重要です。
どのような行為がカスハラに当たるのか、従業員に周知しておく必要があります。
カスハラ発生時は、初動対応として被害に遭った従業員を顧客から速やかに引き離し、状況を落ち着かせることが第一です。必要であれば、担当者を交代させたり、相手に退去を求めたりすることも検討します。
記録と証拠保全として、通話録音や来客対応の記録、チャットログなど、カスハラの内容を詳細に記録し、証拠を保全することも欠かせません。
加えて、法務、人事、産業医、そして警察など、外部の関係機関と連携するフローをあらかじめ定めておきましょう。
カスハラに対する相談窓口の設置方法は下記の記事で詳しく解説しています。

3.教育・研修・対応マニュアル化と記録の徹底
カスハラ対策は、従業員一人ひとりの意識を高めることから始まります。
役割別のトレーニングが必要です。 顧客と直接接する現場の従業員はもちろん、管理職や本社窓口担当など、それぞれの役割に応じたカスハラ対応研修を実施します。
マニュアルの作成では、カスハラの想定問答集や、NGな対応、過去の事例をまとめ、従業員間で共有するのがおすすめです。
さらに、記録の自動化とアラート機能通話録音システムなどを導入し、カスハラの発生を自動的に記録・検知する仕組みを構築することで、迅速な対応が可能になります。
カイクラでは、社労士監修のカスハラ対策に役立つ資料を用意しています。カスハラ対策に必要な実務についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
\社労士が監修!/
カスハラ対策の資料をダウンロード
▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説
カスハラ労災を未然に防ぐ仕組みづくり

カスハラへの対策は、被害が発生してからおこなう「事後対応」だけではなく、未然に防ぐための「事前準備」も重要です。ここでは、カスハラが起きにくい環境を整え、従業員を守るための仕組みづくりを解説します。
- カスハラの発生を防ぐための環境の見直し
- カスハラの証拠を残すための設備を整える
- 産業医・社労士・弁護士と連携する
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.カスハラの発生を防ぐための環境の見直し
従業員が安心して働ける環境を整えることが、カスハラ予防の第一歩です。
顧客からの問い合わせが集中する時間帯や、従業員が一人で対応する状況は、カスハラのリスクを高めます。繁忙期にはバックアップ要員を配置し、一人で顧客対応させないようにするなど、体制を見直しましょう。
受付や相談スペースを遮音性の高いものにしたり、不審者が侵入しにくい防護設備を整えたりすることも重要です。また、危険を感じた際にすぐに避難できるルートを確保し、警備会社や警察への緊急連絡導線を明確にしておきましょう。
2.カスハラの証拠を残すための設備を整える
カスハラが発生した場合に備え、客観的な証拠を記録できる体制を整えることも欠かせません。
とくに、電話でのカスハラは、会話内容が残りづらいため、通話録音システムの導入が有効です。たとえば、カイクラなどのツールを導入すれば、通話内容が自動で録音され、証拠として管理できます。

なかには、特定の人物に対してカスハラをおこなう人もいます。たとえば、女性が電話にでると「性的なことを言う」などです。

カイクラでは、受電時に誰からの電話かわかるようになっており、特定の顧客に対してタグ付けも可能です。タグ付けとは、顧客の情報をタグで分類し、そのタグを検索条件に指定できる機能です。
たとえば、過去にカスハラをおこなった顧客にタグを付けることで、受電時にカスハラの経験があることがわかり、ベテラン社員が電話に出るなどの対策が取れます。
カイクラの詳細は、以下よりご確認いただけます。
\電話対応の負担が減ったとの声多数!/
カイクラの通話録音機能をチェック
▲無料ダウンロード資料あり
3.産業医・社労士・弁護士と連携する
専門家との連携は、カスハラ対策をおこなううえで欠かせません。
産業医には従業員のメンタルヘルスケアを、社会保険労務士には労災手続きを、弁護士には法的な対応を依頼するなど、それぞれの専門分野に応じた役割分担を明確にしておきましょう。
また、どのようなケースで専門家に協力を求めるべきか、具体的な判断基準をフローチャートなどで定めておくようにしましょう。たとえば、「暴言が3回以上繰り返されたら」「身の危険を感じる言動があったら」など、具体的な基準を設けます。
従業員の命や安全に関わる重大な事案が発生した場合、警察へ相談する際の判断軸も、専門家の意見を踏まえて明確化しておきましょう。
カスハラ労災に関するよくある質問

カスハラ労災に関して、よくある2つの質問にお答えします。
- 休業時の補償・療養の扱いを知りたい
- 労災かどうか判断するために相談できるところは?
とくに休業時の補償は安心して療養するためにも知っておきたい内容です。詳しくみていきましょう。
1.休業時の補償・療養の扱いを知りたい
カスハラが原因の精神障害で労災認定された場合、労災保険からさまざまな給付が受けられます。
代表的な給付が、休業(補償)給付と療養(補償)給付です。
休業(補償)給付は、労災の療養のために仕事ができず、賃金を受けられない場合に支給されます。休業した4日目から、1日につき「給付基礎日額」の80%(保険給付60%+特別支給金20%)が支給されます。
療養(補償)給付は、業務上の傷病の治療を受ける際に、その費用が支給される制度です。通院にかかる費用は、実費が支給されます。
これらの給付は、労働基準監督署長が労災と判断した場合に受けられるものです。
2.労災かどうか判断するために相談できるところは?
カスハラ被害に遭い、労災申請を検討している場合は、まず専門機関に相談することをおすすめします。
労災保険に関する相談は、最寄りの都道府県労働局が窓口です。厚生労働省のウェブサイトで所在地一覧を確認できます。
参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省
労災保険に関する相談をしたい場合には、相談ダイヤルがあります。電話番号は、0570-006031です。労働者、事業主のどちらでも相談可能となっています。
参考:労働保険 労災保険相談ダイヤル
まとめ:カスハラは労災になる前に対策しよう

本記事では、カスハラが原因の精神障害が労災認定される可能性、2023年の認定基準改正ポイント、具体的な申請手順、そして企業が取るべき対策を解説しました。
労災認定では、カスハラが原因の精神障害は、業務による心理的負荷として労災認定される可能性があります。2023年の基準改正で、その判断がより明確になりました。
カスハラによる労災を発生させないためにも、相談窓口の設置や研修の実施、通話録音システムの導入など、カスハラの発生を未然に防ぐための仕組みづくりが必要です。
カスハラは、従業員の心身の健康を損なうだけではなく、企業の生産性や信用にも影響を与えます。労災となる前に、従業員を保護し、安心して働ける環境を整えることが、企業にとって最も重要な責務となります。
カスハラ対策を始める際には、以下のお役立ち資料もご活用ください。
\社労士が監修!/
カスハラ対策の資料をダウンロード
▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説













